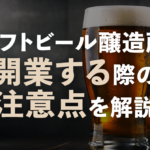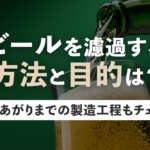ホップクリープとはどんな現象?考えられる原因・問題点と対策方法
- 技術・ノウハウ
- 2025.02.21
- 2026.02.16

ホップクリープは、ビールの製造過程でホップが関与して発生する、緩やかな二次発酵現象です。
ホップを追加する段階で発生し、ビールの風味や品質に大きく影響する場合があります。
厳格にビールの品質を管理するためには、ホップクリープの理解が不可欠です。
この記事では、ホップクリープの概要やメカニズム、問題点について解説します。
ホップクリープがビールにどのような影響を与えるのか、ビール製造における重要性についても取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- ホップクリープとは?
- ホップクリームのメカニズム
- ホップクリープの原因
- ホップクリープの問題点
- ホップクリープを防ぐ方法
- ホップクリープは完全に防げるのか?
- ホップクリープとはどんな現象なのかチェックしよう
ホップクリープとは?
ホップクリープ(Hop Creep)は、原材料であるホップの中にある酵素がドライホップによってビールに再添加され、発酵を促進する現象です。
ビールは、酵母が糖分を分解して発酵し、発酵が進むなかで醸造されますが、ドライホップと呼ばれる工程を経るとホップ由来の酵素が新たに糖分を作り、その糖分をもとにして再発酵が行われます。
新たに作られる糖分はごく微量ですが、そのわずかな量でも再発酵によってビールの味わいを変えてしまうのです。
ホップクリープが進む条件として、ホップの投入量、投入後の時間、液体温度の3点が挙げられます。また、ホップの種類や使用部位によっても影響度が異なります。
主発酵が終了してからドライホップを施す場合は、ホップクリープによってアルコール度数が変わったりドライな仕上がりになったりする可能性があるため、この現象に注意しなければなりません。
ホップクリープによって引き起こされる影響には、以下のようなものがあります。
- フレーバーに影響が出る
- 過炭酸になる
過炭酸とは、パックビールで過剰な炭酸ガスが発生する現象を指します。
容器が破裂するリスクや、過剰な炭酸によって飲みにくくなることがあります。
関連記事:クラフトビールに欠かせないホップ!役割と代表的な種類をチェック
ホップクリームのメカニズム
ホップクリープは、ドライホップの工程で発生する現象です。
ドライホップとは、ビールにアロマを付与し、ホップの豊かな風味を反映させるための手法です。
ビールを通常の工程で発酵させ、発酵中の低温タンク内にホップを投入します。
一次発酵中、または一次発酵終了直後にホップを添加するのが一般的な方法です。
このとき、ホップ内の酵素であるα‐アミラーゼ、β‐アミラーゼ、アミログリコシターゼ、限界デキストリナーゼがビール中の高分子多糖を分解し、再発酵を促します。
投入するホップの量が多いほど再発酵が進み、アルコール濃度の上昇やオフフレーバー(※)、過剰な炭酸ガスが生成されます。
※本来のにおいとは異なる異臭・不快臭。
ホップクリープの原因
ホップクリープの原因として考えられる要素は次のとおりです。
- 温度
- 時間
- ホップの量
- ホップ品種
- ホップの加工
- ビールそのもの
これらの要素について詳しく見ていきましょう。
温度
ホップクリープは、一次発酵中や一次発酵直後にホップを添加した際に発生する酵素活性を指します。
酵素が活発に働く条件として、温度が一因になると考えられています。
温度が高い状態でドライホップを行うと、ホップ内に含まれる酵素のうちアミラーゼが活発に働いて、ビール内に残留している糖を分解し、再発酵を促してしまうのです。
再発酵を防ぐためには、タンク内の温度を低温に保つ必要があります。
酵素の活性が起きないようにこまめに温度を確認し、ビールの安定性を保つことが大切です。
関連記事:発酵温度がビールに与える影響とビールの発酵に適した温度
時間
ホップクリープは、温度だけでなくホップ添加後の経過時間も要因のひとつです。
ドライホッピングによってタンク内のビールはホップと接触しますが、この接触時間が長いほど、投入したホップに含まれる酵素がビール側に作用しやすくなります。
ホップ内にはアミラーゼなどの酵素が含まれているので、ビール内の糖を分解して再発酵を促すおそれがあります。
ドライホップは、再発酵を避けるために長時間行わないよう注意しなければなりません。
一般的に、発酵後48〜72時間以内にドライホップを行い、香りづけすることが理想です。
発酵後48〜72時間以内に行うことが推奨され、比較的短期間でドライホッピングを完了させる必要があります。
しかし、厳格に時間を管理することで酵素の活動が抑えられ、ビールの安定性が維持できます。
ホップの量
ドライホップの工程では、ビールに求める仕上がりに合わせてホップの量を調節します。
ホップ量が多いほどホップクリープが発生しやすいため、1バレル当たり約6.5g程度の使用量が理想です。
ホップを大量に投入すると、中に含まれている酵素の量も増えて、ビールの中の糖を分解しホップクリープを引き起こします。
そのため、酵素活性を抑えるためにも少量のホップでドライホップを行うことが推奨されています。
ドライホップでは、ホップの形態も酵素活性に影響すると考えられています。
使用されるホップの形態としてはペレットやリーフがありますが、ペレットを添加すると発酵が一時的に高まる可能性があります。
一方、収穫したままのリーフを使用する場合は、香りづけに時間がかかるため、ペレットより効率が低い点がデメリットです。
ホップの量だけではなく形態も考慮し、どの程度の香りづけを行うか考えながら投入量を調節する必要があります。
ホップ品種
ホップクリープを引き起こす要因に、使用するホップの品種も挙げられます。
ホップの種類によっては酵素活性が高く、ビールの残留糖分を分解して再発酵を促すため、複数のホップを組み合わせるなどの対応が必要です。
アメリカンホップやニュージーランドホップと呼ばれる種類はアミラーゼが多く含まれており、ホップクリープのリスクが考えられます。
ただし、アミラーゼが多いからといって使用を避ける必要はなく、酵素活性を高めない温度管理や投入量の工夫が重要です。
一方、ホップの投入量が決まっている場合は、品種の選定に注意を払う必要があります。
また、投入するホップの形態も酵素活性に影響するため、「品種」と「形態」の組み合わせに注意が必要です。
関連記事:ケトルホップとは?苦味のあるビール製造に適した種類もチェック
ホップの加工
ホップの加工とは、収穫した状態のリーフ(ホールホップ)を加工し、品質を保つために乾燥させた「乾燥ホップ」や圧縮された「ペレット」にする方法です。
いずれもホップとしての機能をもっていますが、加工されたホップを使用する場合はホップクリープのリスクに注意しなければなりません。
ペレットは収穫したリーフを乾燥・圧縮したものですが、加工の過程で酵素が活性化しやすく、ドライホップの工程でビールに投入すると糖分の分解が一時的に進みやすくなるといわれています。
加工済みのペレットに比べてリーフは酵素活性が低いため、ホップクリープのおそれは低い傾向にありますが、香りの添加効率がペレットよりも低い点がデメリットです。
ペレットと同様に、濃縮液体タイプのホップ(ホップエクストラクト)や、異性化してエキス状に加工されたものもドライホップに使用できます。
加工方法の違いとビールに与える影響を理解したうえで形態を選択することが、ホップクリープの予防に効果的です。
ビールそのもの
ホップクリープの原因は、ホップだけでなくビールそのものにもある場合があります。
ビール内に残存する糖分が多い場合、ホップの投入によって糖分の分解が進み、再発酵を引き起こすリスクが高まります。
高糖度のビールや発酵が未完了のビールでは、特に注意が必要です。
また、ビールは醸造の過程でアルコール度数やpH値に違いが生まれますが、この違いも酵素活性に影響を与えます。
低pH値のビールは酵素の働きが抑えられやすく、高pH値では酵素の活性が高くなるといったケースです。
アルコール度数が高いビールでは酵母の活動が鈍くなり、逆にアルコール度数が低いビールでは酵母が活発に活動しやすくなります。
ホップクリープの予防にはビール側の要因も十分に考慮し、ドライホップの工程を総合的に管理しなければなりません。
ホップクリープの問題点
ホップクリープの問題点として、「フレーバーに影響が出る」「過炭酸になる」という2点が挙げられます。
それぞれの問題点についてみていきましょう。
フレーバーに影響が出る
ホップクリープの問題点の一つが、フレーバーへの影響です。
ホップクリープが発生すると、酵素の働きによってビール内の糖分が再発酵し、アルコール度数の上昇や炭酸ガスの生成が起こります。
炭酸量やアルコールの増加によってビールの風味が変化し、通常の味わいが崩れてしまうのです。
ホップ特有の香りが強調されたり、元の風味が隠れてしまったりすることで、ビール本来の魅力が損なわれる場合もあります。
広く知られているビールの風味が、再発酵によって大きく損なわれてしまうと、飲む人にとっては『思っていた味と違う』『いつもの味ではない』『炭酸が強すぎる』といった否定的な感想につながる可能性があります。
フレーバーの変化は、繊細な風味を楽しむビール愛好家を失望させる原因にもなります。
品質を一定に維持するためには、ホップクリープを防ぐための管理が不可欠なのです。
過炭酸になる
ホップクリープの問題点の一つに、「過炭酸」があります。
過炭酸とは、ビール内の炭酸ガス(CO₂)の含有量が高くなる現象です。
ホップクリープが発生すると、ビール内の糖分が再発酵して炭酸ガスが追加生成され、炭酸ガスの量が過剰になりやすいのです。
過炭酸状態となったビールは、泡立ちが過剰になり、注ぐ際に扱いづらくなります。
口にすると刺すような口当たりとなり、強い刺激が飲みやすさを損なう可能性もあり、ビールの風味が大きく変わり、アロマの繊細な香りや味わいが損なわれることがあります。
このため、醸造者はホップクリープを防ぐために適切な品質管理が求められます。
ボトリング後にガス圧が上昇しすぎる
ホップクリープが深刻な問題となるのは、瓶詰めや缶詰のあとに内部のガス圧が急激に上昇する場合です。
発酵が完全に終わったと判断して充填しても、ホップに含まれる酵素の働きで残った糖分が分解され、瓶の中で再び酵母が活動を始めることがあります。
その結果、炭酸ガスが過剰に発生し、容器内の圧力が想定以上に高まります。
この現象は品質面だけでなく、安全面でも大きなリスクです。
圧力に耐えきれずキャップが吹き飛んだり、栓を開けた瞬間にビールが勢いよく噴き出すこともあるからです。
輸送中に温度が上がった場合や長期保存をした場合には、そのリスクがさらに高まります。
最悪のケースでは瓶の破裂を招くこともあり、消費者に危険が及ぶ可能性も否定できません。
また、過剰なガスの発生はビール本来のバランスを崩す原因にもなります。
香りや味わいが変化し、意図しない酸味や刺激を強く感じられることがあります。
ブルワリーにとっては返品や信頼の低下につながり、クラフトビール市場全体の発展にも悪影響を及ぼす深刻な問題です。
こうしたリスクを避けるためには、ボトリング前の発酵管理を徹底し、温度や残糖値を細かく確認することが重要です。
さらに、パスチャライゼーション(加熱殺菌)やフィルトレーション(ろ過)などの処理を適切に組み合わせることで、ガス圧上昇のリスクを効果的に防げます。
ホップクリープを防ぐ方法
ホップクリープを防ぐ方法は「パスチャライゼーション」「低温ドライホップ」「ドライホップ前の遠心分離」「ドライホップ量の調整」の4点です。
どのような手法で予防できるのか、詳しくみていきましょう。
パスチャライゼーションで酵母の活動を停止させる
パスチャライゼーションは「低温殺菌」という意味の言葉で、ビールの安定性を保つ手法です。
このプロセスでは、ビールを60〜72度に加熱し、短時間維持して酵母や酵素の活動を停止させます。
酵母・酵素の活動が抑えられるため、ホップクリープのリスクを低減します。
パスチャライゼーションは、ビールの保存性の向上と品質の維持にも貢献する方法です。
ドライホッピングのあとにパスチャライゼーションを行うと、ホップの影響による風味の変化を抑えられます。
低温でドライホップする
ドライホップは通常、低温環境下で行われます。
これは、ドライホップを高温の状態で実施すると、酵素が活性化し再発酵が促されやすくなるためです。
10度以下の低温でドライホップを行うと、酵素の活性と再発酵のプロセスが効果的に抑えられるといわれています。
再発酵を防ぎ、アロマの香りづけに特化することで、香りの成分が際立ち、風味がさらに引き立つ手法として知られています。
ドライホップ前に遠心分離を行う
ドライホップの前に遠心分離を実施し、ビール内の不溶性物質を除去する手法です。
ビール側に酵母やたんぱく質といった不溶性物質が含まれると、ホップに問題がなくてもホップクリープが発生するおそれがあります。
遠心分離器でビールの液体から不溶性物質を除去し、クリアな状態でドライホップを実施することで、酵素活性のリスクが低減され、再発酵のリスクが抑えられます。
ビール自身の透明度・清澄度と外観が向上するため高品質な状態が維持され、ビールロスを削減する効果も期待できる方法です。
ドライホップの量を調整する
ドライホッピングの際にホップの使用量を計測し、ビールのスタイルや風味に合わせたて量を決める手法です。
ホップの量が多いほど再発酵が促進されやすくなるため、適切な使用量を事前に設定し、余分な再発酵を防ぎます。
ペレットやリーフといったホップの形態を考慮することで、ホップクリープの予防効果をさらに高められます。
ホップクリープは完全に防げるのか?
ドライホップによるホップクリープを完全に防ぐことは難しいですが、対策を講じることでリスクを軽減できます。
低温でのドライホップやパスチャライゼーション、ホップの品種や形態、投入量の調整といった工夫は、ホップクリープの予防に有効です。
ホップクリープの発生を考慮し、ドライホップのスケジュールを計画することも効果的な予防策です。
ドライホップの効果
ドライホップはホップクリープの原因の1つとされていますが、同時にビールの香りや風味を大きく高める効果もあります。
柑橘やトロピカルフルーツのような華やかな香りは、多くのクラフトビールファンを魅了しています。
そのため、「ドライホップ=悪」と決めつけるのではなく、目指す味やスタイルに合わせて使い分けることが重要です。
適切な方法を選べば、ホップクリープを抑えながら理想的なアロマを引き出すことも可能です。
ドライホップの種類
ドライホップにはいくつかの種類があり、形状や処理方法によって香味の出方やホップクリープの影響度が変わります。
ここでは代表的な2つの種類を紹介します。
- ペレットホップ
- ホールホップ
それぞれの特徴を知ることで、仕上げたいビールのスタイルに合わせた選択が可能になります。
次に、具体的な違いを確認していきましょう。
ペレットホップ
ペレットホップは、収穫したホップを乾燥させ、粉砕したうえで小さな粒状に圧縮したものです。
保管や輸送が容易で、酸化しにくく品質を安定させやすいため、世界中のブルワリーで広く使われています。
さらに、表面積が広いことから香味成分の抽出効率に優れており、比較的少ない量でも強いアロマや苦味を引き出すことが可能です。
効率を重視する大規模生産では欠かせない存在といえるでしょう。
しかしその一方で、粉砕の過程で酵素が表面に出やすくなるため、ホップクリープが進行しやすくなるリスクもあります。
とくにドライホップとして使用すると、残糖の分解が進みやすくなり、ガス圧やアルコール度数が設計どおりにならないこともあります。
そのため、使用量や投入のタイミングを適切に調整し、低温で管理するなどの対策が必要です。
効率性とリスクの両方を理解したうえで、ペレットホップを扱うことが求められます。
ホールホップ
ホールホップは、収穫後に乾燥させただけの自然に近い形状のホップです。
見た目は円錐状で、ホップ本来の構造が残っているため、伝統的な香りや柔らかいアロマを与えるのが大きな魅力です。
とくにクラシックなビールスタイルや、ホップの個性をじっくりと楽しみたいブルワリーで選ばれることが多く、手作業での投入や管理を好む小規模醸造所でもよく利用されています。
一方、ペレットホップと比べると抽出効率が低いため、同じ効果を得るには多めの量が必要です。
また、保管や輸送の際にかさばりやすく、酸化のリスクも高くなるため、取り扱いが難しいデメリットもあります。
ただし、粉砕されていないため酵素の溶け出しは比較的穏やかで、ホップクリープの進行もペレットホップほど強くありません。
そのため、リスクを抑えつつ自然な香味を楽しみたい場合にはホールホップが適しています。
伝統的なスタイルを再現したいブルワリーにとっても重要な選択肢です。
ホップクリープが起きやすいビールの種類
ホップクリープは、とくにドライホップを多用するスタイルのビールで頻繁に見られる現象です。
代表例としてあげられるのは、ダブルIPAやヘイジーIPAのように大量のホップを後半工程で加えるタイプです。
これらのビールは華やかでジューシーなアロマを特徴とし、多くのクラフトビールファンを惹きつけていますが、その裏側で酵素が活発に働きやすい条件がそろっています。
結果として残糖の分解が進みやすく、ボトリング後にガス圧が想定以上に高まったり、フレーバーが意図しない方向へ変化したりすることもあるでしょう。
また、セッションIPAやアメリカンペールエールのように、比較的軽やかなスタイルでもホップの投入量が多ければ同様のリスクが生じます。
ホップの香りを最大限に引き出すための手法が、そのままホップクリープの発生条件と重なるためです。
とくに小規模ブルワリーでは冷蔵保管や流通管理の体制が十分でないこともあり、リスクがさらに高まる傾向もあります。
一方で、ラガーや伝統的なエールなど、ドライホップをほとんど行わないスタイルではホップクリープが問題になる可能性は低いです。
つまり、ビールのスタイル自体がホップクリープの発生しやすさを左右する大きな要因となります。
ホップの使い方を見直すことで、リスクを最小限に抑えながら香味を引き出す工夫が求められます。
ホップクリープとはどんな現象なのかチェックしよう
今回は、ドライホップで発生しやすいホップクリープの原因や対処方法について紹介しました。
醸造者は、ビールに求められる風味・スタイルに合わせてホップを選び、正しい時間管理のもとにドライホップを実施しなければなりません。
再発酵を完全に防ぐことは難しいですが、原因を把握することで予防は可能です。
ビールとホップの状態に注意を払い、適切な方法で品質管理を行うことが重要です。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
コンビタンクブリューハウスの製品説明はこちら
発酵タンクの製品説明はこちら
この記事の監修者
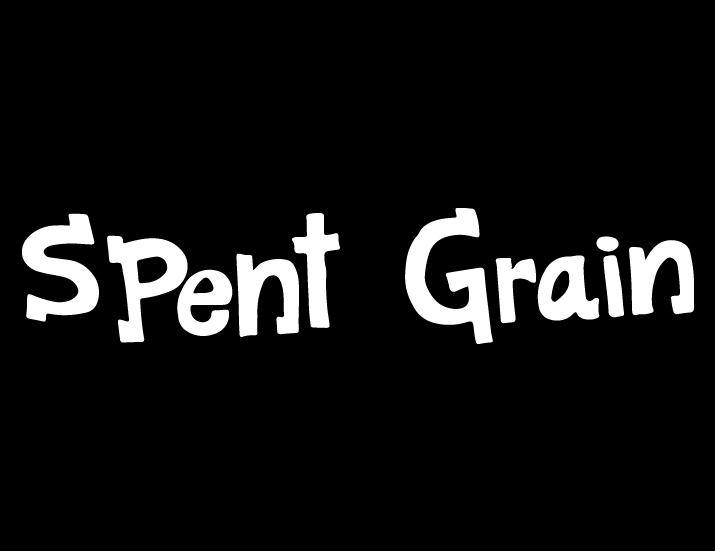
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。