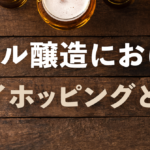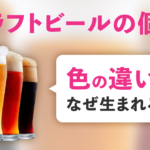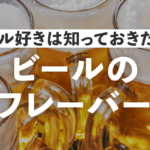ビールに発生する濁りの原因とは?成分や材料による原因と対処方法
- 原材料
- 2025.02.21
- 2025.12.19
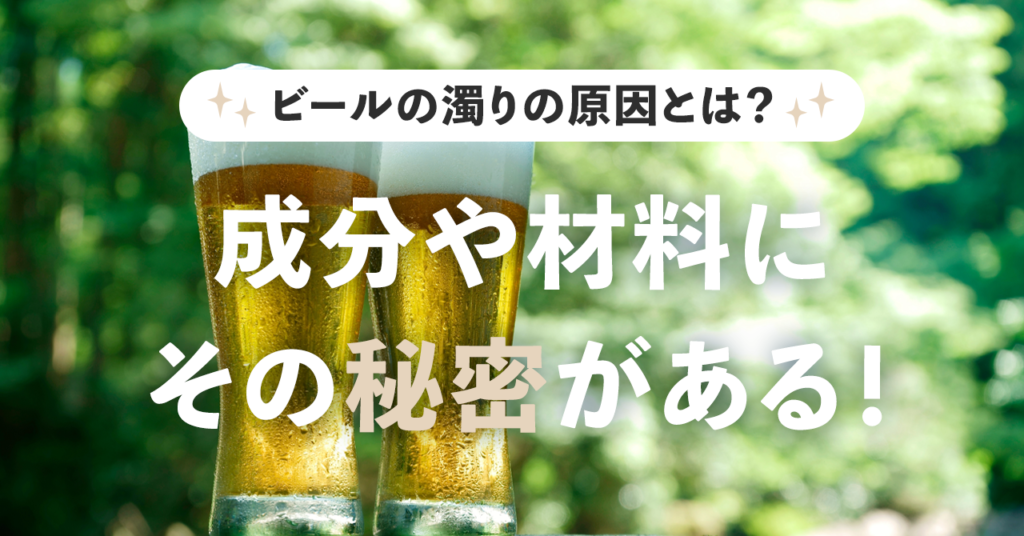
世界中で愛飲されているビールは、透き通った黄金色の液体に細かい泡が浮かび、すっきりとしたのどごしにホップの香りが楽しめるイメージがあります。
しかし、ビールには琥珀色や銅色といった濃色や、濁りが出る種類・条件もあるため、すべてのビールが透明な外観というわけではありません。
製法や管理方法によって品質が変わるため、本場の醸造所では厳格な品質管理のもとでビールを製造しています。
この記事では、ビールに濁りが発生する理由について詳しく取り上げます。
濁りの原因や少なくする方法、濁りが特徴のビールなどについて解説しますので、ビールを楽しむ際の参考にしてください。
【目次】
- なぜビールが濁るのか?
- ビールの濁りの原因
- ビールの濁りを少なくする方法
- 濁りやすいビールの特徴
- 濁りが売りのビールはある?
- Hazy IPAの作り方
- フィルタリング
- ファイニング
- 遠心分離
- 自然沈降
- ろ過していない
- たんぱく質とポリフェノールが多い
- 製造過程で糖分が多く残る
なぜビールが濁るのか?
ビールが濁る理由は大きく分けて生物学的濁りと非生物学的濁りの2種類が挙げられます。
生物学的濁りはバクテリアなどの微生物によるものですが、ビールの製造は多くの場合厳重に品質管理されているため、発生頻度は低いといえます。
一方、非生物学的濁りは『たんぱく質』『酵母』『ポリフェノール』といった成分によるものとされています。
非生物学的濁りは製造工程や原材料の割合といった繊細な条件でも発生することがあります。
ビールの液体に溶けて存在し、分子の大きさと数によって濁りの程度が変化します。
クラフトビールの一部では、風味を保つためにフィルタリングと呼ばれる工程をあえて行いません。
そのため、本来はフィルターでろ過される物質がそのまま残り、液体が濁ります。
濁りのあるビールのうち、正しく管理・製造されて品質に問題のないものは、独特の風味や口当たりが楽しめます。
次からは、ビールに濁りが発生する原因について、成分ごとにみていきましょう。
関連記事:クラフトビールの個性!色の違いはなぜ生まれるのか
ビールの濁りの原因
ビールの濁りは、醸造工程における課題のひとつです。
本来クリアな液体であるべき製品が濁った場合には、濁りの原因を特定する必要があります。
濁りが発生しやすい理由のひとつに、生物学的濁りと呼ばれるものがあります。
これは、野生酵母などの生物が発酵中や発酵後のビールを汚染することで発生する濁りです。
反対に、非生物学的濁りと呼ばれるものとして、ポリフェノールやたんぱく質といった成分が沈殿することで濁りのようになる現象もあります。
ここからは、非生物学的濁りとして多くみられるたんぱく質・酵母・ポリフェノールの変化をみていきましょう。
たんぱく質
たんぱく質は、ビールの原材料の一種であるモルト(麦芽)や大麦、小麦の祖先種であるスペルトなどに含まれる成分です。
生産国ごとにビールの色味や味わいが異なるように、モルトの種類によってもたんぱく質の含有量は異なります。
たんぱく質が多くなるとアルコールの元となる糖化がスムーズに進まないため、たんぱく質を分解する工程が必要です。
しかし、たんぱく質がポリフェノールと結合すると沈殿物が形成されやすくなるため、濁りが発生した場合は遠心分離器によって固形物を取り除かなければなりません。
酵母
発酵中のビールには、大量の酵母が存在し代謝を行っています。
発酵が終わりに近づくと、酵母は塊を作って底に沈殿します。この性質は『凝集性』と呼ばれます。
酵母は発酵に欠かせないもので、自然沈降によってある程度の量は取り除くことができますが、一部がビールの液体中に浮遊し続けると濁りが発生します。
浮遊した酵母が取り除かれない場合、液体中で発酵を続けることがあり、製品の味や品質に影響を及ぼす可能性があります。
ただし、濁りがあっても直ちに品質に悪影響を与えるわけではありません。
酵母自体は強い還元作用をもつため、ビールの酸化を防いで品質を維持し、また、ダイアセチル(※)の再分解を促す作用も期待されます。
※酵母や乳酸菌が発酵する過程で作られる有機化合物のこと。ビールから発せられる異臭の原因となる
ポリフェノール
ビールに使われるホップなどの原材料には、タンニンなどのポリフェノールが含まれています。
ポリフェノールがたんぱく質と結合すると、沈殿物を形成し、濁りの原因になります。
また、ビールの液体を0度まで冷やすと、3度を下回ったあたりからたんぱく質とポリフェノールが結合する「チルヘイズ」と呼ばれる現象も引き起こします。
チルヘイズが起きると液体に白いもやがかかったようになり、泡立ちが悪くなり、濁りが消えず、風味も損なわれやすくなります。
この現象は、通常のビール醸造で頻繁に起きる現象ですが、軽度の濁りであれば、品質に大きな影響を及ぼすことはありません。
ビールの濁りを少なくする方法
ビールの濁りを抑えるには、いくつかの方法があります。
代表的な対処法は次のとおりです。
フィルタリング(ろ過)は、ビールの液体をフィルターに通して不溶性物質を除去する方法です。
醸造過程で溶けきらなかった物質が残る場合、物理的にろ過を行うことで液体をクリアな外観にすることができます。
ファイニングは、清澄剤(せいちょうざい)と呼ばれる濁りを除去する物質を用いて、液体中の浮遊物を凝固・沈殿させる方法です。
ファイニングに使われる清澄剤にはアイシングラスと呼ばれるコラーゲンの一種や、アイリッシュモスと呼ばれる海藻を原料とする添加物などが挙げられます。
遠心分離は、遠心分離器を使用して固形物を強制的に分離する方法です。
自然沈降は、遠心分離とは異なり、ビールを低温・加圧下で貯蔵して固形物を自然に沈殿させる方法です。
これらの方法でも固形物が残る場合には、複数の手法を組み合わせることがあります。
一例として、自然沈降で大部分の固形物を取り除いたあとにフィルタリングを行い、濁りの程度を減らすといった方法があります。
濁りやすいビールの特徴
濁りやすいビールの特徴は、次の3点です。
それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。
ろ過していない
フィルタリングによってろ過されていない液体は、浮遊物がそのまま漂い濁った状態になります。
フィルタリングによって機械的に酵母を取り除くことで、味や見た目が安定し、品質も向上します。
また、汚染物質が混入すると、ビールの味わいや風味だけでなく品質を損なう可能性があるため、ろ過のプロセスは重要です。
フィルターの種類によって異なりますが、耐食性があり、ビールの品質に影響を与えないものを使用することで、安全に浮遊物を除去できます。
たんぱく質とポリフェノールが多い
ビールは麦芽やホップから作られますが、原材料の品種によってはたんぱく質とポリフェノールが豊富に含まれます。
豊かな風味につながる一方で、これらの成分は結合しやすいため、結合してより大きな塊となり目に見えるようになります。
モルト化されていない小麦や大麦など、たんぱく質を多く含む原材料を使うビールは特に濁りが発生しやすいため注意が必要です。
製造過程で糖分が多く残る
ビールは発酵によって糖がアルコールと炭酸ガスになります。
しかし、完全に糖分がなくなるわけではなく、高分子の炭水化物・ガム質が混濁し、短期的に濁りを生じることがあります。
ビールの原材料にはでんぷんや多糖類、βグルカンが含まれるため、この炭水化物混濁が発生します。
炭水化物による混濁は、チルヘイズや生物的混濁とは異なり、炭水化物やガム質によるものです。
ビールをクリアな外観に仕上げるためには、原材料の成分とその特性を理解し、適切な方法で浮遊物を取り除く必要があります。
濁りが売りのビールはある?
濁りはビールだけでなく、日本酒などの酒類にもみられる一般的な現象です。
ビールの中で濁りを売りにしている種類としては、「Hazy IPA(ヘイジー・アイピーエー)」というビールが挙げられます。
インド向けに開発されたペールエールからさらに派生したスタイルで、濁りのあるオレンジ色にクリーミーな泡が乗った個性的な外観をしています。
Hazy IPAの作り方
Hazy IPAは、あらかじめ濁りやすい原材料を使用します。
ドライホップの実施・小麦やオーツ麦を使用することで、ジューシーな風味と個性的な外観に仕上がります。
3つの段階に分けて詳しい作り方をみていきましょう。
ドライホップの実施
Hazy IPAでは、発酵中に熱を加えずホップを投入する『ドライホップ』という工程が必要です。
この作業では、ホップの香りのみがビールに付くため豊かな香りとまろやかな飲み口ができあがります。
アロマ感の強いビール作りには、ドライホップの工程が欠かせません。
小麦やオーツ麦を使用
Hazy IPAには、小麦やオーツ麦(えん麦)が使用されています。
このうち、オーツ麦には多糖類であるβグルカンが含まれており、糖化中に液体の粘度を高める作用があります。
Hazy IPAのまろやかでジューシーな飲み心地を実現するため、小麦やオーツ麦などの穀物を使用する必要があります。
無ろ過
濁りを完全に取り除こうとすると、Hazy IPAの個性的な外観ではなくなってしまいます。
そのため、製造過程ではろ過を控えるか、一切行わず濁りを残します。
ビールの濁りにはさまざまな理由がある
今回は、ビールに濁りが発生する理由や対処法、濁りを特徴とする種類について紹介しました。
ビールの濁りは、たんぱく質とポリフェノールの結合や急速な冷却などの原因で発生します。
これらの要因を管理し、フィルタリングや自然沈降といった方法を用いることで、濁りを抑え、クリアな外観に仕上げることができます。
濁りの有無はビールの見た目だけでなく、味や風味にも影響を与えるため、高品質なビールを製造する際には重要なポイントといえます。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
この記事の監修者
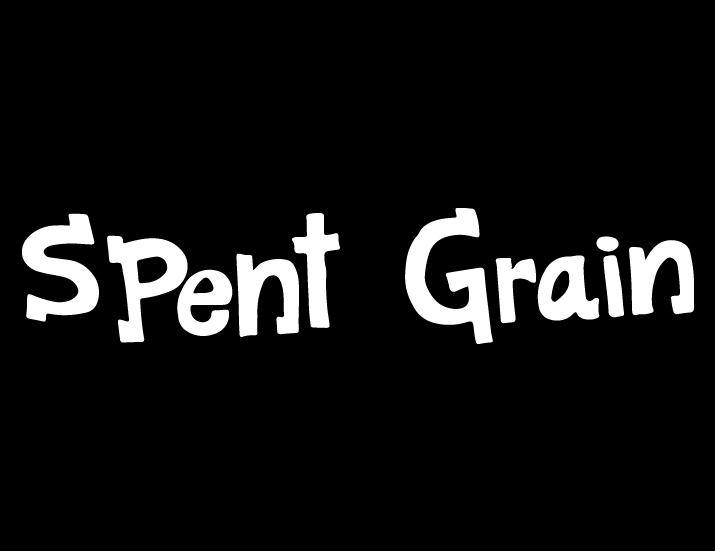
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。