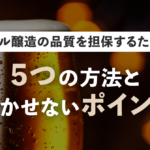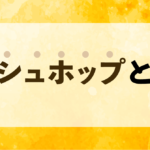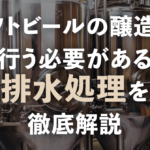ビールのつくり方とは?工程ごとに詳しく解説!
- 技術・ノウハウ
- 2025.09.08
- 2025.12.19

ビールは世界中で親しまれている飲み物ですが、一杯ができあがるまでには緻密な工程が存在します。
原料の組み合わせや工程の進め方によって、風味や香りは大きく変化するものです。
この記事では、ビールに使われるおもな原料と製造工程を紹介し、日々の一杯がどのように生まれるかをひも解きます。
飲むだけでなく、つくる背景にも関心を向けることで、ビールの楽しみ方はより深まるでしょう。
ビールの原料
ビールの味と香りは、おもに4つの原料によって決まります。
- 麦芽
- ホップ
- 水
- 酵母
それぞれの原料は異なる役割を持ち、ビールに個性ある味わいをもたらします。
以下では各原料がどのような働きを担っているのか、詳しく説明していきましょう。
麦芽
麦芽はビールの甘味や香ばしさを支える基盤です。
大麦を発芽させたあと、乾燥させて酵素を活性化したものが麦芽です。
この酵素がデンプンを糖に変換し、酵母が発酵しやすい状態を整えます。
焙煎の強さによってビールの色や香りが変化し、淡いゴールデンビールから深い黒ビールまで幅広い表現が可能です。
麦芽の品質が悪いと、糖の変換がうまくいかず発酵も停滞しやすくなるでしょう。
麦芽の種類には「ピルスナーモルト」「ミュンヘナーモルト」「カラメルモルト」などがあり、組み合わせ次第で色味や風味に深みが出ます。
副原料としてトウモロコシや米を加える方法もありますが、麦芽だけで味をつくる伝統的な醸造方法は、多くの職人にとって王道とされています。
ホップ
ホップはビールに欠かせない苦味と香りを生む重要な原料です。
麦芽の甘さを引き締め、後味にすっきりとした印象を与えてくれます。
抗菌作用によって雑菌の繁殖を抑え、ビールの保存性を高める働きも担います。
投入するタイミングや量、品種の選び方によって、柑橘や草木のような香りを引き出すことも可能です。
ホップの工夫がなければ、個性的なビールは生まれにくいかもしれません。
アロマホップは香りを際立たせ、ビターホップは苦味を強調するなど、それぞれの役割の理解が求められます。
アメリカンホップのシトラやカスケード、ドイツ産のハラタウなど、世界中には個性豊かなホップが存在しています。
水
水はビールの90%以上を占める主要成分です。
ミネラル分を多く含む硬水では苦味が際立ち、ドライでシャープな味に仕上がります。
一方、軟水を使うとまろやかで優しい飲み口になる傾向があります。
実際、ヨーロッパの伝統的なビールは、その土地の水質によって個性が形づくられてきました。
水の選び方をおろそかにすると、理想的な味わいにはなりません。
関連記事:ビールの醸造における水の重要性を解説!
酵母
酵母は糖をアルコールと炭酸ガスに変える生きた微生物です。
この発酵工程こそが、ビールに多彩な香りと味の複雑さを加えます。
上面発酵酵母を使うと、フルーティーで香り高いエール系のビールができ、下面発酵酵母を使うと、クリアで爽快なラガーができます。
使用する酵母の種類や発酵温度の管理によって、同じ原料からまったく違う風味をつくることも可能です。
発酵環境を整備できなければ、予定どおりの仕上がりにはならないはずです。
さらに近年では、ベルギー酵母や自然酵母など独自の個性を持つ酵母も注目されており、酵母そのものがビールの“主役”になるケースもあります。
酵母を選ぶという行為は、スタイルを決めることに直結するといえるでしょう。
ビールのつくり方
ビールづくりは、いくつもの工程を順に進めていきます。
各段階は密接に関係しており、どれか1つでも不十分だと品質に影響が出ます。
基本的な流れは次のとおりです。
- 製麦(浸麦・発芽・焙燥)
- 仕込み(粉砕・もろみづくり・糖化・濾過・煮沸)
- 発酵
- 熟成
- 熱処理
- 充填
この章では、まず製麦と仕込みにフォーカスして解説します。
製麦
製麦は、大麦を麦芽へと変える初期工程です。
酵素の力を引き出すために必要なステップであり、発酵の成功を左右します。
浸麦
大麦を水に浸して発芽の準備を整えます。
一定時間水に浸すことで、種子の内部が均等に潤い、自然な酵素活性が促されます。
水温や浸漬時間の調整が不十分であれば、カビや雑菌のリスクが高まるでしょう。
この段階での管理が、製麦全体の成功を左右する要となります。
発芽
吸水した大麦が発芽を始めると、酵素が活発に働き始めます。
デンプンを糖へ分解する準備が整い、糖化に必要なのがこの工程です。
芽が伸びすぎると雑味の原因にもなるため、適切なタイミングで次の工程に移る必要があります。
発芽の見極めには、経験に基づいた感覚と数値管理の両方が欠かせません。
焙燥
麦を乾燥させれば発芽を止めるため、保存性が高いです。
このときの温度調整によって、麦芽の風味や色合いが決まります。
焙燥が強ければ香ばしさや濃い色も出ますが、軽く仕上げればすっきりとしたビール向きとなります。
乾燥が不十分なまま次の工程に進めば、雑菌の繁殖を招きやすくなるでしょう。
仕込み
仕込みでは、麦芽の糖分を抽出し、ホップを加えて麦汁をつくります。
香りや苦味の基礎がこの段階で形づくられます。
粉砕
乾燥させた麦芽を適度な粒度に粉砕します。
細かすぎれば濾過が詰まりやすくなり、粗すぎると糖分の抽出効率が低下します。
狙ったビールのスタイルに合わせて、粉砕の設定を変えてください。
安定した麦汁を得るには、機械の調整と定期的な確認が求められるでしょう。
もろみづくり
粉砕した麦芽を温水と混ぜ合わせ、酵素の働きを促す工程です。
温度帯ごとに異なる酵素が作用し、デンプンが糖へと変化していきます。
均一に加温されなければ、糖化に偏りが生まれ、発酵が不安定になる可能性も否めません。
工程が進むほど微調整が難しくなるため、ここでの対応が後の結果に大きく影響します。
糖化
もろみを一定温度に保ち、糖分への変換を進めます。
おもにアミラーゼ酵素が活躍し、アルコール発酵に不可欠な糖を生み出します。
糖化が進むと液体が甘くなり、独特の麦の香りが漂ってくるのが特徴です。
この工程を丁寧に行うことで、発酵の段階でトラブルが起きにくくなります。
また、温度帯によって酵素の働き方が異なり、64〜68℃の範囲で細かく調整する必要があります。
酵素が分解する糖の種類によって、ビールのボディ感やアルコール度数が変わるため、思い描く味に合わせた温度の設計が必要です。
少しのズレが風味に影響するため、糖化こそ“職人の腕”が試される部分といえるでしょう。
濾過
糖化された液体から、かすを取り除いて透明な麦汁を得る作業です。
フィルターの性能や濾過スピードによって、雑味の混入を防げます。
不完全な濾過では苦味や濁りが残り、味に一貫性を持たせられません。
使用される濾過槽(ラウタータン)は構造が複雑で、目詰まりや流速のムラが発生することもあります。
こうした問題を防ぐには、麦芽の粉砕度やもろみの粘度管理など、前段階からの連携が重要になります。
濾過は一見単純に見えますが、ミスがそのまま次工程に持ち越されるため、精度が求められる工程です。
煮沸
麦汁を煮沸して殺菌し、同時にホップを加える工程です。
煮沸の長さやタイミングで、香りの出方や苦味の強さが大きく変わります。
温度を一定に保ちつつ、余分な揮発成分を飛ばすことで、クリアな味わいへと導けます。
ホップは煮沸の早い段階で加えると苦味が強くなり、終盤に入れると香りが残りやすいです。
この“投入タイミングのさじ加減”が、ホップの個性を最大限に引き出す鍵となります。
さらに煮沸中にはたんぱく質が凝固して沈殿する「ホットブレイク」現象が起こり、これが濁りや腐敗の原因を減らしてくれます。
煮沸は見た目以上に、物理や化学の知識が必要な工程です。
発酵
発酵は、麦汁に酵母を加え、糖をアルコールと炭酸ガスへ変換する工程です。
この段階でビールの種類ごとの特徴が決まっていきます。
発酵温度が高ければ香りが豊かでフルーティーな仕上がりになります。
反対に温度が低ければ、キレのあるすっきりとした味わいになりやすいです。
酵母の種類によっても、出てくる香りや風味がまったく異なってくるのが面白いところです。
発酵中はガスや泡の状態を見ながら、慎重に温度管理を行う必要があります。
気を抜いてしまえば、雑菌の混入や酸化のリスクが高まり、品質の低下を招いてしまうでしょう。
酵母が活発に働きすぎると、思わぬ副産物が発生して風味が崩れることもあります。
そのため、発酵タンクの構造や冷却装置の性能も含めて、設備選定の段階から最適化しておくことが大切です。
熟成
発酵が終わったばかりのビールは、味に角があり、香りも荒々しい状態です。
熟成を通じて雑味を落ち着かせ、なめらかな口あたりへと導きます。
冷却したタンク内で静かに時間をかけることで、酵母の働きが落ち着き、香り成分が整理されていきます。
数週間〜数か月の熟成期間を取ることで、香味のバランスが整い、丸みを帯びたビールに仕上がるでしょう。
しかし、熟成が長すぎると香りが飛んでしまったり、狙っていた個性が失われるおそれもあるため、最適な期間の見極めが求められます。
この工程を省略してしまうと、ビールの完成度が格段に落ちてしまうといっても過言ではありません。
最近では熟成方法の違いによって、ウイスキー樽やワイン樽で仕込まれたビールも登場しており、香りの幅をさらに広げる試みが進んでいます。
熱処理
熟成後のビールを安定的に保つためには、微生物を殺菌する工程が必要です。
それが熱処理です。
ビールを一定温度で加熱することにより、酵母や雑菌の活動を停止させ、賞味期限を延ばします。
過熱しすぎると風味を損なうため、加熱温度や時間には十分な注意が必要です。
反対に加熱が不十分であれば、商品として流通する中で味が変質してしまうおそれがあります。
なお、加熱を行わずに仕上げる「生ビール」もあり、その分冷蔵保存や輸送においてより高度な管理が求められるといえるでしょう。
最近では無濾過・非加熱の“クラフト感”を活かした商品も増えており、消費者の嗜好によって熱処理の有無を使い分けるケースが増えています。
充填
ビールの仕上げとして行われるのが、容器への詰め作業です。
缶・瓶・樽などの容器へと充填し、商品として出荷される段階に入ります。
このとき避けなければならないのは「酸化」です。
外気に触れることでビールの味が急速に劣化するため、無酸素状態で素早く封をする必要があります。
最近では窒素ガスを用いて酸素の侵入を防ぐ設備も増え、品質管理は年々進化しています。
また、充填後の保管温度も重要で、高温下では風味の持ちが悪くなるため、一定の温度で管理し続ける体制が欠かせません。
とくに小規模な醸造所では、手動や半自動の設備を使うこともあり、オペレーションに慣れていないと微細なミスが風味の差につながることがあります。
高品質な状態でビールを届けるには、最終工程のこの部分こそ慎重に取り組む必要があるといえるでしょう。
まとめ
ビールは、麦芽・ホップ・水・酵母という4つの原料が必要です。
しかし、それぞれの素材の選定と製造工程の細やかな調整で、味わいや香りに驚くほどの違いをもたらします。
製麦では酵素の活性を高め、仕込みで麦汁を整え、発酵によって個性が生まれ、熟成で角が取れていきます。
一杯のビールを完成させるには、さらに熱処理と充填が必要です。
これらの工程は単なる作業ではなく、造り手のこだわりと経験、品質への責任が詰まった連続の判断ともいえるでしょう。
ビールづくりを本気で考えるのであれば、「設備」「流れ」「管理項目」をただ知るだけでは足りません。
現場で培われた知見やトラブル対応の引き出し、さらには法規制への理解や設備選定のノウハウが求められます。
私たちスペントグレインでは、これから醸造所開業を目指す方向けに、以下のようなサポートを提供しています。
- 開業規模や予算に応じた醸造設備の提案と設計
- 現役ブルワーによる研修や現場実習
- ビールの製造から販売までを想定した全体フローの構築支援
導入すべき機材の選定に悩んでいる方や、製造工程の管理に不安を感じている方は、一度ご相談ください。
どのようなスタイルのビールを、どのような人に届けたいのか。
その思いを、経験豊富なスタッフが一緒に形にしていきます。
ビールづくりの第一歩は、知識を得ることから始まりますが、実現するには“環境と人”が欠かせません。
理想のブルワリー開業へ向けて、スペントグレインがその一歩を後押しいたします。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
この記事の監修者
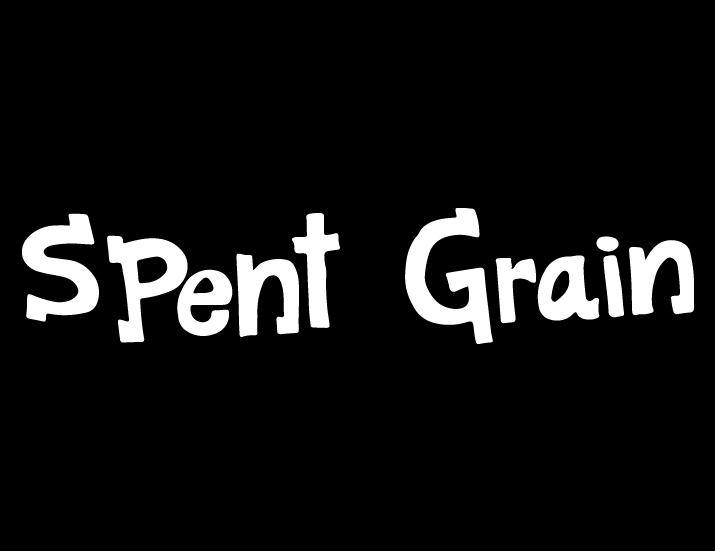
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。