下面発酵と上面発酵の違いと各発酵方法でつくれるビールの特徴
- 技術・ノウハウ
- 2024.10.30
- 2026.02.16
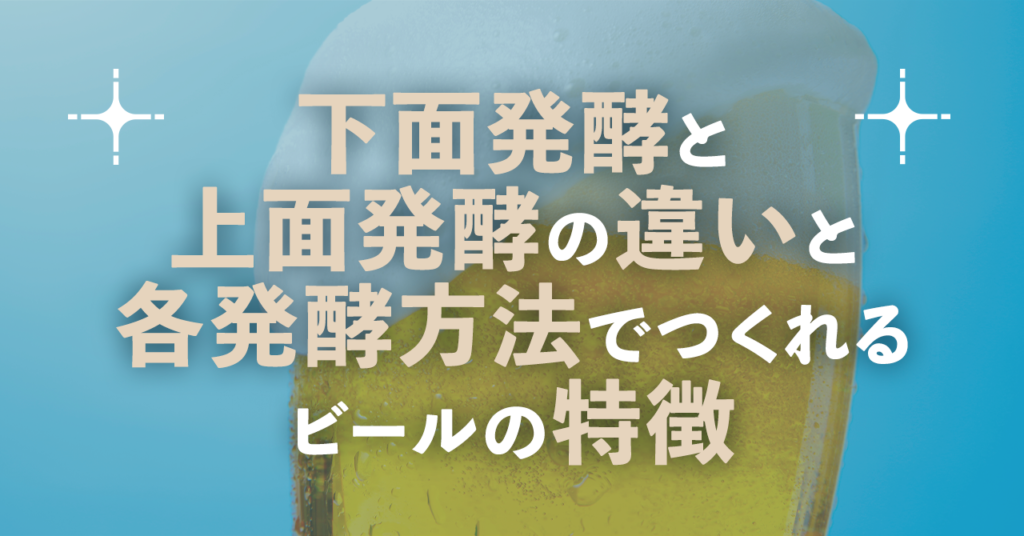
「ビールの発酵について理解を深めたい」「下面発酵と上面発酵の違いを教えてほしい」などと考えていませんか。
両者の特徴がわからず、困っている方もいるでしょう。
下面発酵と上面発酵では、用いる酵母の種類や発酵温度が異なります。
また、完成するビールにも、さまざまな違いが生じます。
ここでは、下面発酵と上面発酵の違いを解説するとともにこれらの方法でつくれるビールの特徴を紹介しています。
ビールのつくり方が気になる方は参考にしてください。
【目次】
クラフトビールの発酵とは
基本的なビールの醸造工程は次の通りです。
【ビールの醸造工程】
- 麦芽(発芽した大麦)を製造する
- 麦芽を細かく砕き温水と副原料を混ぜるなどして麦汁をつくる
- 麦汁に酵母を加えて発酵させる(若ビールをつくる)
- 貯蔵庫で若ビールを熟成させる
- ビールを瓶や缶へ詰める
クラフトビールの発酵は、麦汁に酵母を加えて発酵させる工程です。
酵母は、糖をエサにアルコールと炭酸ガスを生み出す微生物といえるでしょう。
したがって、発酵過程で麦汁に含まれる糖がアルコールと炭酸ガスに分解されます。
発酵工程を終えた液体を若ビールといいます。
若ビールは味、香りとも研ぎ澄まされていないため、貯蔵庫での熟成を必要とします。
関連記事:クラフトビールの品質管理の方法は?3つの検査を紹介
ビールの発酵に使用されるビール酵母とは
ビールの味や香りを大きく左右するのは酵母です。
酵母は糖をアルコールと炭酸ガスに変えるだけでなく、エステルやフェノールなどの香り成分も生み出します。
ラガーの爽快感は、下面発酵酵母が低温で活動することによって生まれます。
一方、エールの複雑で華やかな香りは、上面発酵酵母が多様な成分を生成するためです。
ベルギーのランビックに使われる野生酵母は、空気中や木樽にいる菌を取り込み、酸味や奥深い風味を加えます。
このように、酵母の違いが世界中のビールの多様性を生み出しているのです。
下面発酵と上面発酵の違い
ビールの発酵は、次の3つに分かれます。
【3つの発酵】
- 下面発酵
- 上面発酵
- 自然発酵
ここでは、主な発酵方法である下面発酵と上面発酵について解説します。
下面発酵
発酵が進むと、タンクの底に沈む酵母を用いる方法です。
上面発酵との大きな違いは発酵温度です。
下面発酵は、10度前後(5~15度)の低い温度(低温)で発酵させます。
酵母の働きが緩やかになるため、上面発酵に比べて発酵に時間がかかります。
目安の期間は7~10日程度です。
また、発酵後に行う熟成(=貯蔵)にも時間がかかります。
目安の期間は30日程度です。
ちなみに「貯蔵」を英語で「lager」といいます。
したがって、長期熟成を必要とする下面発酵でつくられたビールを「ラガービール」と呼びます。
ラガービールは、現在のビール約90%を占めるといわれています。
上面発酵
発酵が進むと、麦汁の上部に浮き上がる酵母を用いる方法です。
上面発酵の発酵温度は20度前後(15~25度)です。
下面発酵よりも高い温度(常温)で発酵させます。
酵母の働きが活発になるため、短時間で発酵を終えられます。
目安の期間は3~4日程度です。
未熟臭の原因になる物質が少ないため、長期熟成も必要としません。
上面発酵でつくるビールを「エールビール」といいます。
エールビールの「エール」は穀物でつくるお酒を意味します。
エールビールは、古くからつくられてきた伝統的なビールです。
ラガービールが主流となっていますが、イギリスなどでは現在でも高い人気を誇ります。
関連記事:発酵温度がビールに与える影響とビールの発酵に適した温度
エールビールとラガービールの歴史
エールビールとラガービールは、古くから多くの方に愛されてきたビールです。ここでは、これらの歴史を紹介します。
エールビールの歴史
エールビールは、歴史が豊かなビールです。
イギリスでは、5世紀に入ってエールという呼び名が定着したと考えられています。
また、9世紀に入ると巡礼者向けの飲食施設として、道路沿いにエールハウスが建ち並びました。
ちなみに、15世紀まで、エールはホップを加えていない醸造酒、ビールはホップを加えた醸造酒を指します。
18世紀に入るとこの区別はなくなります。
エールの人気を高めたのが、18世紀に登場したポーターとその後に登場したペール・エールです。
しかし、19世紀に入りラガービールが普及すると人気は徐々に失われます。
とはいえ、完全に人気を失ったわけではなく、現在でも個性豊かな味わいを求めるファンが多数存在します。
ラガービールの歴史
ラガービールは、ドイツのバイエルン地方で15世紀に誕生したと考えられています。
ただし、低温発酵、低温貯蔵を必要とするため、急速に普及したわけではありません。
ラガービールは、主に冬のドイツやチェコでつくられていました。
状況を変えたのが、19世紀に登場した冷蔵技術です。
温度管理を行えるようになったことで、世界中でつくられるようになりました。
これに伴い、人気が高まります。
現在のシェアは約90%と考えられています。
エールビールとラガービールの特徴
エールビールとラガービールは、どのようなビールなのでしょうか。それぞれの特徴を紹介します。
エールビール
豊かなコクと芳醇な香りを特徴とするビールです。
ここでいうコクは、麦汁の濃い味わいといえるでしょう。
芳醇な香りは、さまざまな要素で成り立っています。
その中のひとつといえるのが、上面発酵酵母が生み出す香気成分です。
具体的な香りは、用いる酵母、用いる酵母の量、発酵温度などで異なりますが、果実のような香りを楽しめるビールやスパイスのような香りを楽しめるビールなどがあります。
ワインと同じく、香りと味わいを楽しむビールといえるかもしれません。
風味を引き出すため、あまり冷やさず飲むこともあります。
ラガービール
爽やかなキレとホップの苦味を特徴とするビールです。
ここでいうキレは、アルコールと炭酸ガスが生み出すスッキリ感、あるいはのど越しといえるでしょう。
低温で発酵させるため、エールビールに比べて香りは穏やかです。
エステルや高級アルコールなどの香気成分が少ないためと考えられます。
以上の説明からわかる通り、癖が少ないビールです。
自然発酵とは?
続いて、もうひとつの発酵方法である自然発酵について解説します。
自然発酵は、天然の酵母を用いて麦汁を発酵させる方法です。
一般的なビールは、人工培養された酵母を用います。
自然発酵の主な特徴は、個性的な香りなどを生み出せることです。
国内にも自然発酵を用いて製造しているクラフトビールがあります。
お酒の製造方法
アルコール飲料は、その製造過程によって大きく3つに分類されます。
分類を知ることで、ビールがどこに位置づけられるかが理解しやすくなります。
- 醸造酒
- 蒸留酒
- 混成酒
この違いは、風味やアルコール度数、飲まれる文化的背景に大きな影響を与えています。
醸造酒
麦やブドウ、米などを発酵させて造るお酒を「醸造酒」と呼びます。
ビール、ワイン、日本酒がその代表例です。
醸造酒は、原料の個性がはっきりと味に表れるのが特徴です。
たとえば、以下はそれぞれ味わいに大きく影響します。
- ワイン:ブドウの品種
- 日本酒:米や水の質
- ビール:ホップや酵母の選び方
フレッシュな飲み口や土地ごとの風土が反映される点も魅力で、クラフト文化との相性もよいお酒です。
ドイツのヴァイツェンやベルギーのセゾン、日本の地ビールなど、地域ごとに原料や酵母を工夫したビールが多く存在し、それぞれの地域性を反映したスタイルが受け継がれています。
こうしたお酒は観光資源にもなっています。
蒸留酒
蒸留酒は、醸造酒を加熱しアルコール分を取り出すことで生まれます。
代表例はウイスキー、ブランデー、焼酎、ジンなどです。
度数が高く、長期保存や熟成に適しており、木樽で寝かせるとバニラやスモーキーといった奥深い香りを獲得します。
料理との合わせ方も幅広く、少量でも満足感が得られるため、食後酒や特別なシーンに楽しまれることが多いお酒です。
アイルランドのアイリッシュウイスキーやスコットランドのスコッチ、メキシコのテキーラなど、国ごとに法的定義や製法が確立されており、個性が明確です。
なかには数十年熟成させたものもあり、コレクター市場でも高値になることがあります。
混成酒
既存のお酒に果実やハーブなどを加えて仕上げたものが「混成酒」です。
甘みや香りを自由に調整できるため、カクテルのベースとしても広く使われています。
華やかで親しみやすい味わいは初心者にも飲みやすく、近年はクラフトリキュールも人気です。
最近では、国産のボタニカル素材を使ったクラフトジンや、地域特産の果実を使ったリキュールも登場し、種類がますます増えています。
飲みやすさからギフトや女性向けにも人気があり、さまざまな飲み方のアレンジも楽しまれています。
醸造酒の発酵方法
同じ醸造酒でも、発酵の進め方にはいくつかの方法があります。
とくに日本酒やビールでは、発酵方式の違いが品質や味の複雑さに大きく影響します。
代表的な発酵方式は、次の3つです。
- 単発酵
- 単行複発酵
- 並行複発酵
この仕組みを理解することで、お酒の多様性がより鮮明に見えてきます。
単発酵
単発酵は、原料に糖が多く含まれている場合に使われる発酵方法です。
ワインや一部のビールがその代表例で、ブドウや麦芽に含まれる糖を酵母がそのままアルコールに変えます。
工程がシンプルなため、原料の質がそのまま味に反映されます。
たとえば、良質なブドウを使えば高級ワインができるように、素材選びが重要です。
ビールでは、ブロンドエールやゴールデンエールなどのシンプルなレシピがこの方法に当てはまり、素材本来の香りやコクを引き出しやすい傾向があります。
加糖や副原料が少ないため、原材料の質がダイレクトに味に表れます。
単行複発酵
単行複発酵は、糖化とアルコール発酵を順番に行う方法です。
ビール造りでは、まず麦芽の酵素がでんぷんを糖に変え、そのあと酵母が糖をアルコールに変えます。
工程がシンプルで安定しているため、初心者向けのクラフトビールキットなどでもよく使われているのが特徴です。
味わいは比較的ストレートで、素材の違いが分かりやすく楽しめます。
家庭用ビールキットや一部の缶ビール製品でもこの発酵方法が使われており、再現性や安定性の高さから大量生産にも向いています。
クセが少なく、初心者にも親しみやすい風味を作りやすいのが特徴です。
並行複発酵
並行複発酵は、糖化と発酵を同時に進める高度な発酵方法です。
日本酒が代表的で、麹菌がでんぷんを糖に分解しながら、同時に酵母がその糖をアルコールに変えます。
この仕組みによって、甘みや酸味、香りが複雑に絡み合い、深みのある味わいが生まれます。
ビールでも高品質なクラフトビールで使われることがあり、複雑で奥行きのある風味を作り出せるのが魅力です。
日本酒のように工程管理が難しいため、技術を求められますが、温度や発酵速度を調整すると味の幅を広げられます。
ハイアルコールや熟成タイプのビールでもこの方法が使われ、クラフトビールの分野でとくに注目されています。
下面発酵、上面発酵は酵母や発酵温度などが異なる
ここでは、ビールの発酵について解説しました。
下面発酵は、発酵が進むとタンクの底に沈む酵母を用いる方法です。
低温で発酵を行います。
長期熟成を必要とするため、この方法でつくられたビールをラガービールといいます。
上面発酵は、発酵が進むと上部へ浮き上がる酵母を用いる方法です。
常温で発酵を行います。
この方法でつくられたビールをエールビールといいます。
ラガービールは爽やかなキレ、エールビールは芳醇な香りを特徴とします。
ビールを製造する場合は、両者の違いを理解しておくことが大切です。
マイクロブルワリー、クラフトビール開業支援のスペントグレインでは、醸造設備や施工工事だけでなく、酸化防止策の導入や溶存酸素管理のサポートも行っています。
ビールの品質向上を目指す事業者様は、ぜひ弊社へご相談ください。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
コンビタンクブリューハウスの製品説明はこちら
発酵タンクの製品説明はこちら
この記事の監修者
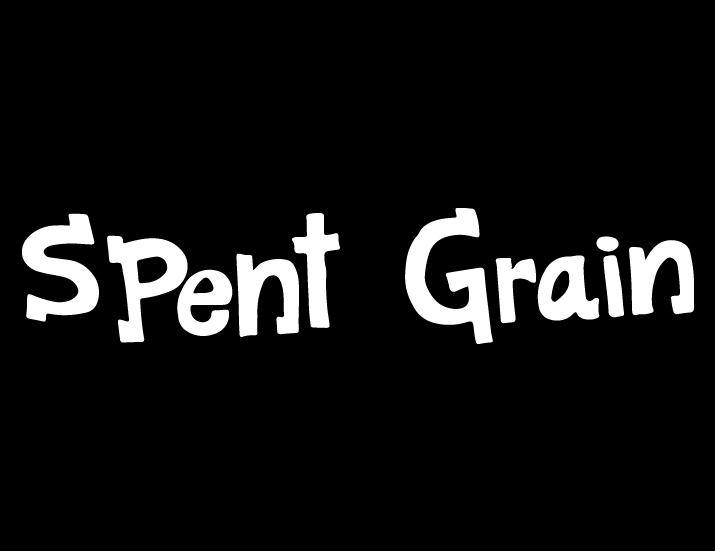
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。









