ビールの殺菌方法とは?クラフトビールの殺菌方法も紹介
- 技術・ノウハウ
- 2025.02.21
- 2026.02.16
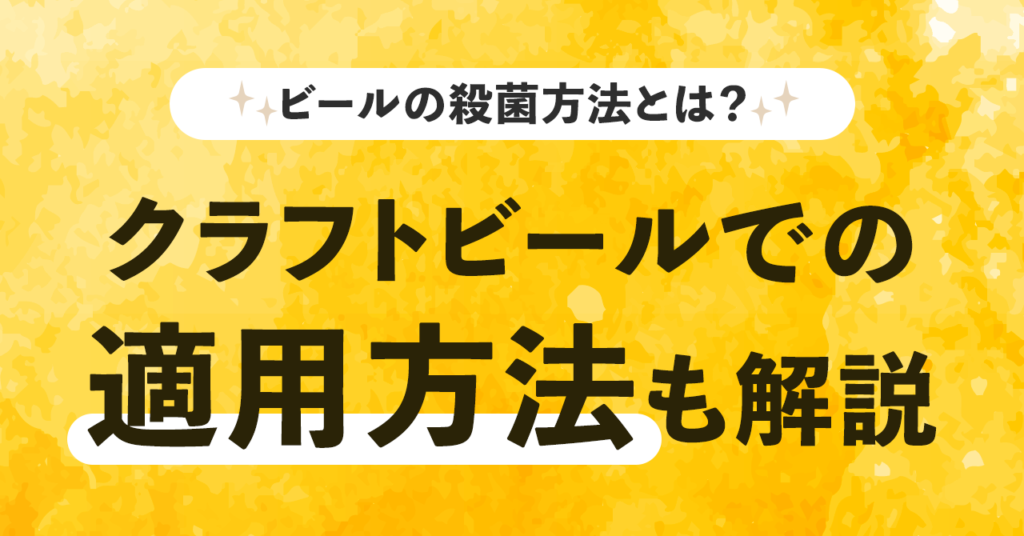
ビールは新鮮でバランスのとれた風味を維持するために、厳重な品質管理のもとで製造されています。
なかでも重要なプロセスが殺菌処理であり、低温殺菌やフィルタリングといった方法で、ビール内の微生物や酵母を殺菌・不活性化します。
熱を加える処理はビールの品質に影響を与える可能性があるため、温度や加熱時間を慎重に調整する必要があります。
この記事では、ビールにおける殺菌方法と低温滅菌のメリットを中心に、クラフトビールで低温滅菌する方法や殺菌処理を行わないビールについて取り上げています。
【目次】
ビールにおける殺菌方法
ビールの製造では、原材料の量や種類の選定・調整に加え、製造工程や品質管理も重要です。
具体的には、次のような方法で微生物や酵素の殺菌を行っています。
【パスチャライゼーション(低温殺菌)】
ビールを60〜72度の低温で数分加熱し、微生物を殺菌して酵素を不活性化する方法です。
有害な微生物のみが死滅し、ビールの風味や栄養価は保たれます。
風味や香りを保ちつつ、保存期間を延ばす効果もあります。
【高温短時間殺菌】
高温短時間殺菌(HTST)は、ビールを72〜85度の高温下で15〜30秒加熱する方法です。
パスチャライゼーションよりも高温で微生物を滅菌し、ビールの品質を保ちます。
熱による影響を考慮する必要がありますが、加熱時間を短くすることで風味の損失を抑えることが可能です。
【滅菌フィルター】
ビールの液体をフィルタリング(ろ過)して微生物を除去する方法です。
加熱を行わないため、熱による風味や香りの損失や変化を最小限に抑えることができます。
クラフトビールなどに用いられることが多く、新鮮な状態を保ちながらも余分なものを取り除く必要があるときに適した方法です。
【紫外線照射】
紫外線(UV)を用いて微生物の遺伝子を損傷させ、構造を変化させることで不活性化および殺菌を行う方法です。
紫外線は熱と違い、ビールの成分に影響せず殺菌だけを行うことができます。
ただし、水分に吸収されると効果が減衰しやすく、完全な殺菌ができない点に注意が必要です。
【超音波殺菌】
高強度の超音波を照射し、微生物や酵母を不活性化する方法です。
ビールの貯蔵寿命を伸ばす効果も期待できますが、商業的には十分に普及していない方法です。
これらの方法を組み合わせることで、ビールの品質や安全性を向上させることが可能です。
低温滅菌のメリット
低温滅菌はバクテリアを殺菌し、酵母の繁殖を防ぎます。
長期保存の際にも低温殺菌は役立ち、品質を損なわず長持ちさせる重要なプロセスです。
バクテリアを殺菌できる
ビール内にはさまざまな種類のバクテリアが存在する可能性があり、低温殺菌によりそれらの活動を抑制または停止させることができます。
バクテリアが活動できなくなることでビールの風味や香りは損なわれず、衛生的な状態が維持できます。
低温殺菌は、未発酵状態の残留糖分が多いビールや、保存期間が長い製品に用いられる方法です。
酵母の余分な繁殖を防ぐ
原材料に含まれる酵母は、糖を分解して発酵を促進します。
しかし、不要な発酵までも促してしまう再発酵(ホップクリープ)と呼ばれる現象を引き起こし、ビールの風味が変わってしまうため、品質を維持管理するためにも酵母の抑制が不可欠です。
そこで、低温殺菌によって酵母の活動を停止させ、余分な繁殖を防ぎます。
酵母の活動が停止することで再発酵のリスクが低減し、ビールの安定性を維持できます。
関連記事:ホップクリープとはどんな現象?考えられる原因・問題点と対策方法
冷蔵せず長期保存が叶う
ビールの低温殺菌は、微生物や酵母を不活性化し、品質が損なわれるリスクを抑えます。
保存期間を延ばす効果も期待できますが、常温で保管すると酸化のリスクが高まるため、冷暗所などの環境で保存することが推奨されます。
また、品質を損なわないためには密閉性の高い容器で保存し、衛生的な環境を選ぶことも重要です。
クラフトビールで低温滅菌する方法
クラフトビールで低温滅菌を行う方法には、『瞬間滅菌』と『トンネルスプレー滅菌』があります。
それぞれどのような方法なのか、詳しくみていきましょう。
瞬間滅菌
瞬間滅菌(パルス滅菌)は、ビールを高温で短時間加熱し、有害な微生物を殺菌する方法です。
加熱後のビールを急速に冷却することで、風味を保つことができます。
トンネルスプレー滅菌
トンネルスプレー滅菌(スプレー滅菌)は、ビールをトンネル状のチャンバーに容器ごと入れ、スプレーで滅菌する方法です。
低温環境で行われるため、加熱による品質劣化が起こりません。
国内外で広く行われている低温殺菌法の一種で、瓶詰め後に殺菌を行う手法としても知られています。
関連記事:ビール醸造の品質を担保するための5つの方法と欠かせないポイント
殺菌しないビールは存在する?
殺菌処理を行っていない状態は、余分な浮遊物をろ過で取り除いた状態、または無ろ過の状態を指します。
通常のビールは熱処理や低温殺菌が施されますが、生ビールと呼ばれるビールは熱殺菌を加えていません。
酵母がまだ生きた状態で残っており、ビール本来のフレッシュな風味が損なわれず豊かな味わいが楽しめます。
食品表示法の『ビールの表示に関する公正競争規約及び施行規則(第4条第2項)』では、熱処理を行っていないビールのみが『生ビール』『ドラフトビール』と表示できると定められています。
※参照元:全国公正取引協議会連合会「ビールの表示に関する公正競争規約及び施行規則」
ビールの品質管理に適した殺菌方法を選ぶ
今回は、ビールの品質管理に欠かせない殺菌方法について紹介しました。
ビールの品質管理にはいくつかの方法があり、殺菌処理は特に重要な工程です。低温殺菌やフィルタリングで微生物や酵母を不活性化し、風味を損なわずに保存期間を延ばす効果が期待できます。
化学物質が使用されることもありますが、化学物質に適さない素材には、熱湯短時間殺菌や滅菌フィルターが利用されます。
一方、殺菌処理をあえて行わず鮮度を保った状態で提供する生ビールのような種類もあるため、品質を適切に管理するためには、殺菌処理の適用条件や方法を確認しておくことが重要です。
マイクロブルワリー、クラフトビール開業支援のスペントグレインでは、醸造設備や施工工事だけでなく、酸化防止策の導入や溶存酸素管理のサポートも行っています。ビールの品質向上を目指す事業者様は、ぜひ弊社へご相談ください。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
コンビタンクブリューハウスの製品説明はこちら
発酵タンクの製品説明はこちら
この記事の監修者
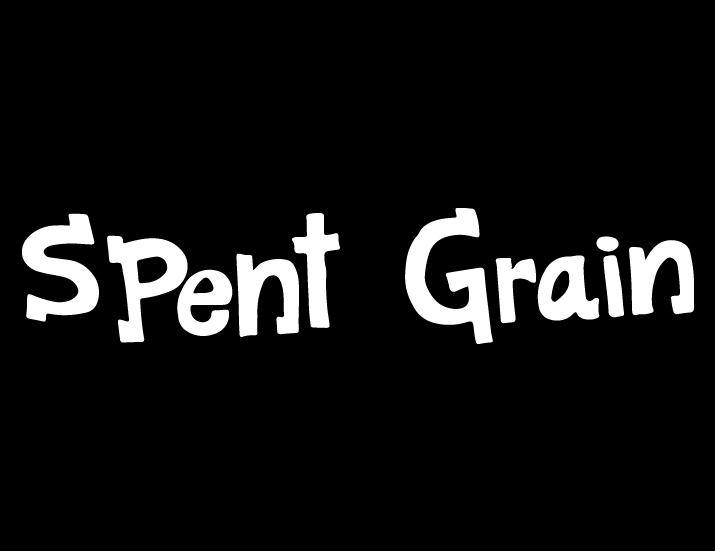
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。









