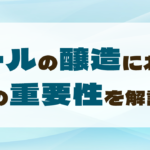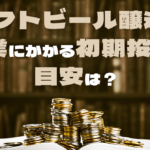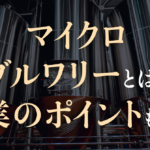ビール醸造家になるには?手続きと費用の内訳を解説
- 開業ガイド
- 2024.06.14
- 2026.02.16
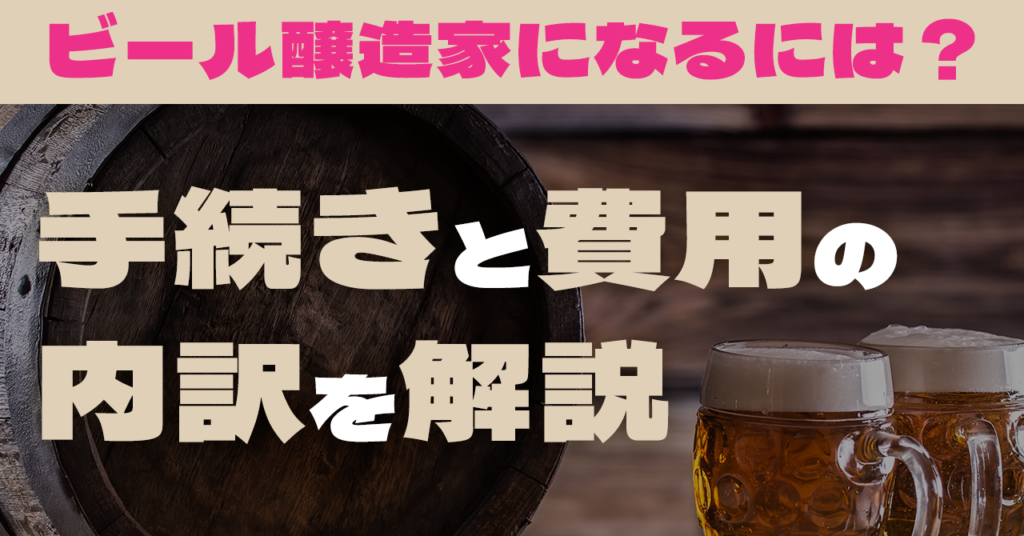
ビールの奥深さに魅了され、「自分でもこだわりのビールを造りたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
ビール醸造家として開業するには、マイクロブルワリーを立ち上げるのが一つの手ですが、どのようなステップで準備を進めていけばよいのでしょうか?
そこで本記事では、ビール醸造家になるために必要な手続きと費用を詳しく解説します。
ビールを造る夢を叶えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
- 醸造所許可の全体像と「何から始めるか」
- ビール醸造家の定義
- ビール醸造家になることの魅力
- マイクロブルワリーを開業するために必要な4つのステップ
- 許可取得のための要件チェックリスト
- 許可取得に直結するコストの考え方
- マイクロブルワリーの開業にかかる費用
- マイクロブルワリーの開業における3つの資金調達方法
- マイクロブルワリーを成功させるための3つのポイント
- ビール醸造家になり、こだわりの溢れたビールを造りましょう
醸造所許可の全体像と「何から始めるか」
ビール醸造家を目指すなら、酒類製造免許の取得が必須です。この免許は酒税法に基づき、製造場の所轄税務署長から交付されます。
以下では、許可取得の流れを押さえるために重要な3つのポイントを解説します。
- 許可の根拠を押さえると要件の抜け漏れを防げる
- 所轄・相談窓口を特定できると手戻りが減る
- 許可区分の違いを把握すると計画の前提が固まる
これらを理解することで、スムーズな免許申請へとつながります。
許可の根拠を押さえると要件の抜け漏れを防げる
酒類製造免許は酒税法第7条に基づき、製造場の所在地を管轄する税務署長から交付されます。免許には「ビール製造免許」と「発泡酒製造免許」の2種類があり、麦芽使用比率が原料の50%以上であればビール製造免許、50%未満であれば発泡酒製造免許が必要です。
免許取得には、酒税法第10条に定められた4つの拒否要件に該当しないことが求められます。
|
要件 |
内容 |
|---|---|
|
人的要件 |
申請者が酒税法違反や税金滞納をしていないこと |
|
場所的要件 |
醸造所が取り締まり上、不適当な場所に設置されていないこと |
|
経営基礎要件 |
事業を継続できる財務基盤があることを証明 |
|
技術・設備要件 |
醸造に必要な技術と設備を保有していることが審査 |
これらの要件を事前に把握しておくことで、申請書類の準備段階で必要な項目を漏れなく整理可能です。要件を満たしていない場合、審査段階で不許可となるリスクが高まるため、申請前の自己チェックが重要です。
所轄・相談窓口を特定できると手戻りが減る
税務署には「酒類指導官」という専門担当者が配置されており、免許申請に関する相談が可能です。酒類指導官は複数の税務署を兼務していることが多いため、事前に連絡してアポイントを取ることが推奨されます。
事前相談では、申請書類の記載方法や設備仕様の確認、製造計画の妥当性について助言を受けられます。とくに初めて免許を申請する場合、書類の不備や記載の不整合が審査遅延の原因となるため、早期の相談が効果的です。相談時には、製造場の図面や設備リスト、事業計画書の草案を持参すると、具体的なアドバイスを得やすくなります。
所轄税務署を早期に特定し、酒類指導官との連携体制を構築することで、申請後の差戻しや追加資料の提出を最小限に抑えられます。
許可区分の違いを把握すると計画の前提が固まる
ビール製造免許と発泡酒製造免許では、最低製造数量基準が大きく異なります。ビール製造免許では年間60kL以上の製造が求められるのに対し、発泡酒製造免許では年間6kL以上で取得可能です。
麦芽使用比率と副原料の配合率によって、どちらの免許が必要かが決まるのが一般的です。ビール製造免許では、麦芽使用比率が50%以上で、副原料の使用は原料の5%以下に制限されます。
一方、発泡酒製造免許では、麦芽使用比率が50%未満、または副原料が5%を超える配合が認められます。製造したいビールのレシピに応じて、適切な免許区分を選択しなければなりません。
事業計画の初期段階で免許区分を明確にし、製造レシピと整合性を取ることが重要です。複数の免許を同時に申請することも可能なため、将来的な製品展開を見据えた戦略的な選択が求められます。
ビール醸造家の定義
ビール醸造家(ブルワー)とは、醸造所(ブルワリー)やビールメーカーで製造を担当する人を指します。
ビール醸造家として起業する場合を除けば、特別な資格は必要ないものの、食品衛生やビール製造に関する幅広い知識が求められます。
マイクロブルワリーでクラフトビールを作る方から、大手のビールメーカーに勤める方もおり、ビール醸造家としての携わり方は人によってさまざまです。
なお、本記事ではマイクロブルワリーでビール醸造家を目指す方に焦点を当てて、情報をお伝えします。
マイクロブルワリーとは
マイクロブルワリーとは、小規模なビール醸造所のことです。
日本では、1994年の酒税法の改正によって、ビールの製造における年間最低製造量が200万Lから6万Lに引き下げられたことを背景に誕生しました。
アメリカでは「年間生産量が約180万Lを下回る規模で、その75%以上を外部へ販売する醸造所」をマイクロブルワリーと定義していますが、日本では明確な定義はありません。
また、マイクロブルワリーのように小規模な醸造所で造る、多様で個性的なビールを“クラフトビール”といいます。
ビール醸造家になることの魅力
ビール醸造家になる魅力は、なんといっても個性溢れるテイストのビールを造ることができる点です。
原材料選びから製造まで、ビール造りの工程すべてに関わることができるため、独特の味わいや香りをもたせることができます。
フルーティーな味わいのものや苦みの強いものなど、ビール醸造家の裁量次第で好きなように造れるなんて、心躍りませんか?
マイクロブルワリーを開業するために必要な4つのステップ
ご自身でマイクロブルワリーを立ち上げよう思い立った場合、どのようなステップのもとに進めていけばよいのでしょうか?
ここでは、マイクロブルワリーを開業するまでの手順を、4つのステップに分けて解説します。
ステップ①醸造スキルを身につける
ビールの製造において、醸造スキルを身につけることが必要不可欠です。
しかし日本では、酒税法によって、アルコール度数1%以上の飲料を、酒類製造免許をもたない人が造ることは禁じられているため、独学でスキルを習得するのは困難です。
そこで、スクールや団体などが実施する醸造研修を受ける、あるいはブルワリーで働くといったかたちで醸造スキルを習得しましょう。
ご自身で習得するのが難しい方は、醸造スキルをもつブルワーを雇い入れるのも一つの手です。
ステップ②事業計画を作成する
醸造スキルを身につける傍らで、事業計画の作成を進めていきましょう。
事業の構想を具体的な計画に落とし込むことで「初期費用がいくらかかるのか」「どのようなビールを造りたいのか」など、事業の詳細をご自身のなかで整理できます。
また、後述する開業資金の調達や酒類製造免許の取得に際して、事業計画書は必須なので、ここで事業の詳細を決定しておきたいところです。
製造したいビールの種類や販売戦略、初期費用の見積もりなどを計画書に書き出し、事業の全体像を描いてみてください。
ステップ③開業資金を集める
事業計画が完成したら、次は資金調達です。
マイクロブルワリーを開業し、ビール醸造家になるためには、物件の賃借や醸造設備の購入、内装工事など、多額の初期投資がかかります。
資金調達の方法は、銀行融資やクラウドファンディングなどいくつかの種類があるので、ご自身に適した方法で資金を集めましょう。
ステップ④物件を選び、ビール醸造設備を整える
マイクロブルワリーの物件選びは、事業を成功に導く重要なステップです。
原材料の供給ルートの確保や、駅やバス停からの交通の利便性の確保など、さまざまな要素を考慮したうえで選ぶ必要があります。
開業する場所が定まったら、醸造設備の準備を始めましょう。
用意すべき醸造設備は、製造するビールや醸造方法によって異なります。
醸造設備を決める際は、性能や耐久性、価格など、ご自身のビール造りとの適合性を吟味して選ぶのが望ましいです。
ステップ⑤酒類製造免許を取得する
上記のステップが済んだら、あとは酒類製造免許を取得するだけです。
所轄の税務署で、事業計画書や醸造スキルの有無に関する書類、ビールのレシピなど、免許取得に必要な資料を、面談を通じながら準備していきます。
マイクロブルワリーでクラフトビールを造る際は、「ビール」と「発泡酒」の2種類から、取得する酒類製造免許を選ぶことになります。
この2種類の大きな相違点は、1年間の最低製造量です。
ビールの酒類製造免許の場合は、1年間に最低でも6万L製造する必要がありますが、発泡酒であれば6千Lの製造で営業が認められます。
そのため、小規模での営業を望む方は、発泡酒の酒類製造免許を取得してもよいかもしれません。
一般的にビールのほうが高級なイメージがありますが、発泡酒でも味の劣らないクラフトビールを造ることができます。
なお、醸造所に飲食店を併設する場合は、保健所から飲食店の営業許可証の取得が必要です。
関連記事:ビールを醸造するために必要な資格とその取得方法を徹底解説
許可取得のための要件チェックリスト
酒類製造免許の審査では、製造計画の具体性・敷地や用途の適合性・衛生動線の明確化という3つの観点が重視されます。審査では、申請書類の記載内容と実際の製造場の状況が一致しているかが厳しく確認されます。
- 製造計画の具体性で「継続性」を説明できる
- 敷地・用途の適合で拒否リスクを抑えられる
- 衛生動線の明確化で現地確認に備えられる
書類と現地の不整合があると、審査が長引いたり不許可となったりするリスクが高まります。
製造計画の具体性で「継続性」を説明できる
ビール製造免許の場合、年間60kL以上の製造計画が最低基準ですが、単に数字を記載するだけでは不十分です。販売先の確保状況や市場調査結果、月別の製造スケジュールなど、実現可能性を裏づける詳細なデータが求められます。
製造計画には、原料の調達方法や製造工程の説明も含まれます。どこから麦芽やホップを仕入れるのか、発酵や熟成にかかる期間はどの程度か、タンクの回転率をどう設定するかなど、実務レベルでの計画を明示することが重要です。これらの情報が不足していると、計画の実現可能性に疑問を持たれる原因となります。
事業の継続性を示すためには、初年度だけでなく3〜5年程度の中期計画も示すことが効果的です。販売数量の増加見込みや新製品の開発計画など、成長戦略を明確にすることで、審査官に対して事業への本気度を伝えられます。
敷地・用途の適合で拒否リスクを抑えられる
製造場の敷地は、都市計画法や建築基準法に基づく用途地域の制限を遵守しなければなりません。工業地域や準工業地域であれば問題ありませんが、住居専用地域では醸造所の設置が制限される場合もあります。物件選定の段階で、自治体の都市計画課に確認し、醸造所として使用可能かを確認しておくことが重要です。
賃貸物件を使用する場合、物件所有者から醸造所としての使用許可を得る必要があります。賃貸借契約書に「酒類製造業としての使用」が明記されていることを確認し、契約書の写しを申請書類に添付しましょう。物件所有者の承諾が得られていないと、免許が交付されても使用できない事態に陥る可能性があります。
製造場と飲食店や販売店を併設する場合、それぞれの区画を分離することが必須です。平面図上で製造エリアと営業エリアを色分けし、動線が交差しないように設計することが求められます。
衛生動線の明確化で現地確認に備えられる
原料の搬入口から製造エリア、製品の出荷口までの動線を明確にし、清潔区域と汚染区域を分離する必要があります。動線図を作成し、作業の流れに沿って衛生管理のポイントを示すことで、審査官に対して適切な管理体制を説明できます。
製造設備の洗浄と消毒の手順、排水処理の計画も審査対象です。現地確認では、これらの設備が実際に機能する状態にあるかが確認されるため、申請前に設備を整えておくことが重要です。
許可取得に直結するコストの考え方
酒類製造免許の取得には、登録免許税15万円のほかに、設備投資や衛生管理のための費用が発生します。これらのコストは単なる初期投資ではなく、審査で「事業の実現可能性」を証明するための必要経費として位置づけられます。
- 衛生関連投資で「適正管理」を示せる
- 設備仕様の根拠で「実現可能性」を補強できる
- 保守体制の見込みで「継続性」を裏づけられる
適切な投資配分と要件に沿った裏付け資料の整備により、要件充足の説明が明瞭になります。
衛生関連投資で「適正管理」を示せる
醸造所の衛生管理には、専用の洗浄設備や消毒設備が必要です。タンクや配管の洗浄に使用するCIPなどの定置洗浄や消毒体制を整えることは、HACCPに沿った衛生管理の実効性を示す有力手段です。必須機器と断定はできませんが、合理的な衛生計画として強く推奨されます。
温度管理設備も衛生管理の一環です。発酵タンクの温度制御システムや冷蔵設備は、品質管理と衛生管理の両面で重要な役割を果たします。温度管理(発酵・貯酒・保管)は品質・衛生の基盤であり、体制を具体化して申請書に示すことが強く推奨されます。
排水処理設備への投資も重要です。醸造工程では大量の水を使用し、有機物を含む廃水が発生します。醸造排水は下水道法・各自治体条例/水質汚濁防止法の基準に適合させることが必要です。設備計画に方針を明示し、必要に応じて所管へ事前協議することで、関係法令適合を示せます。
設備仕様の根拠で「実現可能性」を補強できる
年間60kLの製造計画に対し、1回の仕込み量が300Lのタンクを使用する場合、年間何回の仕込みが必要かを明示しましょう。タンクの数や発酵期間を考慮し、計画どおりの製造が可能であることを数値で証明することが求められます。
設備の購入見積書や発注書を申請書類に添付することで、設備投資の実現性を示せます。見積書や発注書は必須ではない場合がありますが、型番・仕様・納期を示す実現性の裏付け資料として有効です(設備状況・契約書などの写し、必要に応じ追加提出)
見積書には、設備の型番や仕様、納期などの詳細情報を含めることが重要です。架空の計画ではなく、実際に実行可能な計画であることを証明するための裏付け資料となります。
中古設備を使用する場合でも、設備の状態や性能を証明する資料が必要です。整備記録や動作確認の結果を示すことで、中古設備でも計画どおりの製造が可能であることを説明できます。
保守体制の見込みで「継続性」を裏づけられる
定期的なメンテナンスや部品交換のスケジュールを示すことで、長期的に安定した製造が可能であることを証明できます。保守契約を設備メーカーと締結している場合、その契約書を提出することで、より具体的な保守体制を示すこともできるでしょう。
また、故障時の対応体制も計画に含めます。代替設備の確保や修理業者との連携体制を明示することで、トラブル発生時にも事業を継続できる準備があることを示せます。保守費用を運転資金計画に組み込むことで、財務面での継続性も示しましょう。年間の保守費用を見積もり、キャッシュフロー計画に反映させることが重要です。
関連記事:クラフトビールの設備はメンテナンスが重要!ポイントや手順は?
マイクロブルワリーの開業にかかる費用
マイクロブルワリーを立ち上げ、経営していくためには、どのような費用がかかるのでしょうか?
以下では、開業に必要な初期費用を、維持費とともに詳しく解説していきます。
初期費用
マイクロブルワリーを立ち上げる際の初期費用の目安は、2,000万~3,500万円程度です。
初期費用のなかでも、多額になる費目は以下の通りです。
物件取得費
物件を借りてマイクロブルワリーを開業する場合は、保証金や仲介手数料などがかかります。
具体的な金額は、賃貸契約を結ぶ不動産会社によって異なりますが、一般的には、家賃の6~12か月分の保証金と1か月分の仲介手数料の支払いが必要です。
例として、家賃20万円の物件を借りるケースでは、140万~260万円程度が初期費用としてかかります。
醸造設備の導入費用
マイクロブルワリーを開業するためには、麦芽粉砕機や仕込み窯、発酵タンクなど、仕込みから充填するまでの醸造設備を準備しなければなりません。
醸造設備の金額は、規模や購入先のメーカーによって前後しますが、一式揃えるのに1,000万~2,500万円程度かかることが見込まれます。
中古品を購入すれば費用を抑えられますが、ビールの品質は設備に左右されるのでこだわりをもって選びましょう。
内装工事費
物件が確保できたら、醸造設備を設置するための内装工事を施します。
内装工事費は、工事の内容や物件の状況によって異なりますが、少なくとも500万円は見積もっておくとよいでしょう。
DIYが得意な方は、内装工事の一部を自分で行うことで費用を下げられるかもしれません。
維持費
マクロブルワリーは、経営を維持するだけでも毎月の支出があります。
開業を考えるにあたって、毎月の維持費がどのくらいかかるのかを確認しておきましょう。
維持費の費目と、その金額の目安を以下にまとめました。
【維持費の費目と金額の目安(月に750Lのビールを製造する場合)】
| 費目 | 目安 |
|---|---|
| 原材料費 | 45万~50万円 |
| 水道光熱費 | 5万~10万円 |
| 人件費 | 50万~80万円 |
| 家賃 | 地域や物件によって大きく異なる |
維持費の総額は、100万~140万円程度に、家賃を加えた金額が一つの目安となります。
開業して間もないときは収益を得られない可能性もあるので、資金を充分に確保しておくと安心です。
マイクロブルワリーの開業における3つの資金調達方法
マイクロブルワリーの開業には多額の資金が必要なため、何かしらの手段を講じて資金を調達するのが一般的です。
そこで本項では、資金調達の主な3つの方法を紹介しますので、ご参照ください。
方法①銀行から融資を受ける
マイクロブルワリーを開業する際の一般的な資金調達方法として、銀行からの融資が挙げられます。
銀行から融資を受けるための審査では、「事業計画が綿密に立てられているか」「自己資金をどれくらい用意しているのか」の2点が重視されます。
原材料の仕入れ先や資金の使途など、経営に関する資料を豊富に用意することで事業実現性の高さをアピールしましょう。
また、自己資金は、マイクロブルワリーの開業に必要な資金総額のうち、30~50%程度を用意できれば、審査を通過する可能性が高まります。
方法②クラウドファンディングで資金を募る
マイクロブルワリーの開業資金を集める方法として、クラウドファンディングも挙げられます。
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の方から支援を募る仕組みのことで、支援者に対してはリターンとして製品やサービスを提供します。
ビール造りへの熱意をアピールしつつ、ビールを楽しめるリターンを設定すれば、多くの賛同を得られるかもしれません。
ただし、目標金額に達するまで期間を要する可能性や、そもそも目標金額を達成できない可能性も念頭に置いておく必要があります。
クラウドファンディングを利用する際は、余裕のある資金調達の計画を立てましょう。
方法③補助金や助成金を活用する
政府や各自治体は、新規事業を始める方を支援するために、補助金や助成金を提供しています。
たとえば、政府によって実施される「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」は、クラフトビール事業で利用することが可能です。
これらの補助金や助成金は返済が不要な場合もあるので、開業に関わる負担を大幅に軽減してくれます。
ただし、申請には一定の要件があるうえ、競争率も高いため、申請に漏れることがないように事前にきちんと調査し、適切な書類を準備しておきましょう。
マイクロブルワリーを成功させるための3つのポイント
マイクロブルワリーを開業し、多くの方にこだわりのビールを飲んでもらうためにはどうすればよいのでしょうか?
ここからは、事業を成功させる3つのポイントを詳しく紹介していきます。
ポイント①ビールの品質の追求する
マイクロブルワリーを成功に導くカギを握っているのは、ビールの品質です。
クラフトビールは、大量生産されるビールとは異なり、醸造家の手で、一つひとつじっくり向き合って造られるため、品質を追求することができます。
また、消費者もクラフトビールに対して、品質の良さやブルワリーの独自性を求める傾向にあります。
ですので、マイクロブルワリーを立ち上げる際は、扱う設備やビールのレシピにこだわりをもち、品質の追求に尽力しましょう。
ポイント②ブランドの認知度の向上を図る
良い商品を造るだけでなく、多くの人に知ってもらうこともマイクロブルワリーを成功させるためには求められます。
そのためにインターネットを積極的に活用し、多くの人に自社のブランドを認知してもらいましょう。
オンラインショップを開設すれば、遠方の方にも購入していただけるかもしれません。
ご自身の造り上げたビールを消費者に知ってもらい、手に取りたくなるようなマーケティング戦略を行うことが成功につながります。
ポイント③地域に密着したビールを造る
マイクロブルワリーを成功させるには、ブランドの認知度を向上させるのが大事であると説明しましたが、そのために地域性を活かしたビールを造ることも有効な手段の一つです。
地域の食材を活かしたビールや、文化性を取り入れたビールを造ることで地域に根差したブルワリーを目指せます。
また、地域で開催されるイベントに参加して、地元の方と直接的にコミュニケーションを図ることも大切です。
そうすれば、ご自身が醸造したビールがその地域の特産として認知され、地元の方に愛されるのはもちろん、その土地を訪れた方がお土産として購入してくれるでしょう。
ビール醸造家になり、こだわりの溢れたビールを造りましょう
本記事では、ビール醸造家になるための手順と費用の内訳を解説しました。
マイクロブルワリーを開業し、ビール醸造家になるためには、醸造スキルを身につけることや酒類製造免許を取得することなどが求められます。
また、開業の際には、物件の賃借や醸造設備の購入のために2,000万~3,500万円程度の初期費用が必要です。
自己資金で足りない部分は、銀行の融資やクラウドファンディングで資金を調達して、こだわりのマイクロブルワリーを立ち上げましょう。
マイクロブルワリー、クラフトビール開業支援のスペントグレインでは、ビールの醸造に関する経験豊富な3人の現役醸造家が、マイクロブルワリーの開業支援を行っております。
開業に関するあらゆる悩みを解決しますので、まずはご相談ください。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
コンビタンクブリューハウスの製品説明はこちら
発酵タンクの製品説明はこちら
この記事の監修者
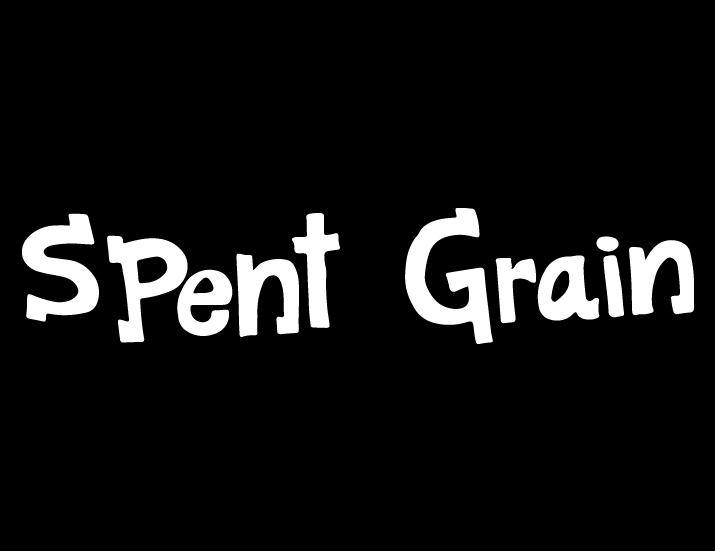
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。