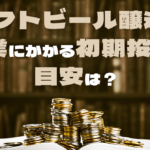ビール製造に必要な免許と取得にかかる費用について
- 開業ガイド
- 2024.06.14
- 2026.02.16
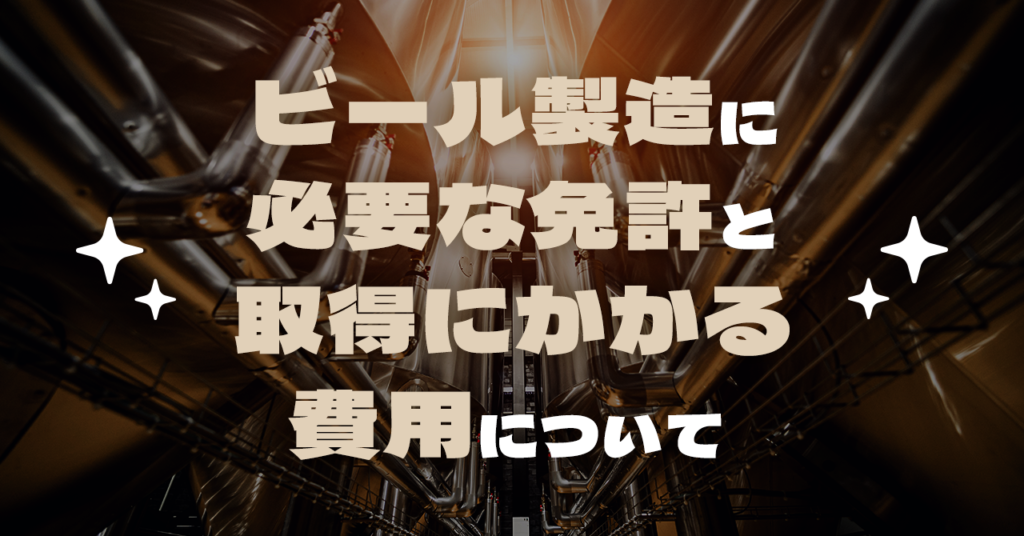
紀元前4,000年前から存在していたとされるビールは、今もなお世界中の愛好家たちの心を掴んで離しません。
そんなビールの製造には、酒類製造免許を取得する必要があることをご存じですか。
免許の申請方法などは、事前に把握しておきたいですよね。
そこで本記事では酒類製造免許とは何か、取得に要する費用も含めて詳細をご紹介します。
ビール醸造所の開業を検討している方や、免許の取得前に情報を集めている方は、ぜひご覧ください。
【目次】
- 酒税法上のビールの定義とは?
- クラフトビールとは
- ビールの製造に必要な酒類製造免許とは
- 酒税法上の「ビール」の定義を押さえる
- 最低製造数量基準の要点(ビールは年60kL以上)
- 酒類製造免許を取得するための要件
- 申請から交付までの流れと登録免許税の扱い
- 食品衛生法とHACCPの整理(酒造への適用)
- 酒類製造免許を取得するための費用と申請方法
- ビール製造免許の登録免許税は免許1件につき15万円
酒税法上のビールの定義とは?
日頃から親しみのあるビールですが、「ビールの定義は?」と聞かれると、言葉に詰まる方も多いのではないでしょうか。
ビールの定義は、酒税の確保と保全を目的に、お酒の分類や製造免許、税率などを取り決めた酒税法によって定められています。
日本の酒税法は下記に示した通り、お酒に使用する原料と麦芽の割合によって、ビールとほかのお酒を区分しています。
【酒税法によるビールの定義】
- 麦芽・ホップ・水を原料として発酵している
- 麦芽を使用する割合が原料全体の50%以上を占める
上記の定義にくわえて、ビールは下記の表にまとめた4項目で細かく分類されますので、ご一読ください。
【ビールの分類】
| 使用する酵母の種類 | ・下面発酵を使ったラガービール ・上面発酵を使ったエールビール |
|---|---|
| 色 | ・淡色ビール ・中濃色ビール ・濃色ビール |
| 原料 | ・原料のみで醸造したビール ・原料と副原料を組み合わせて醸造したビール |
| 出荷時の処理方法 | ・加熱処理されていない生ビール ・加熱処理を行ったビール |
これらの分類を踏まえて、ビールの種類を意味するビアスタイルは、現在180以上あるといわれています。
クラフトビールとは
ビールのなかでも、特に支持を得ているのが「クラフトビール」です。
クラフトビールをひと言で表すなら「小規模メーカーで製造された個性あふれるビール」です。
昔は「地ビール」ともよばれていました。
日本各地のお土産屋さんなどで、特産物や季節限定の副原料を使った多種多様な製品が並んでいるのを、見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
ビール職人がこだわり抜いて作った製品のなかから、自分好みの味や香りを選べる楽しさがあることを理由に、若年層をはじめとした多様性を求める消費者から人気があります。
その人気から、国内の至る所にクラフトビール醸造所が立ち上げられています。
そんなクラフトビールを製造するには、製造免許を取得しなければなりません。
製造免許の内容や取得要件については、以下で詳しくご紹介します。
参照元:全国地ビール醸造所協議会事務局
ビールの製造に必要な酒類製造免許とは
先述したように、ビールを含む酒類の製造、つまりアルコール分1度以上の飲料を製造するには、酒類製造免許を取得しなければなりません。
酒類製造免許が設けられた目的としては、酒税を漏れなく徴収すること、消費者へ円滑に酒類を提供することが挙げられます。
酒類製造免許は、製造する酒類の品目や製造所ごとに、所轄税務署長から授けられます。
お酒の品目ごとに、全17種類の製造免許が設けられていますが、今回は取得基準をビールと発泡酒に絞って、下記の表にまとめましたので、ご覧ください。
【酒類製造免許の取得基準】
| ビール製造免許 | 発泡酒製造免許 | |
|---|---|---|
| 麦芽使用比率 | 原料の50%以上 | 原料の50%未満 |
| 副原料使用比率 | 原料の5%以下 ※認められた原料のみ | 原料の5%以上 |
なお、販売目的だけでなく、自己消費のための製造であっても、酒類製造免許の取得を求められます。
例外として、酒類を製造する際に用いられる酒母やもろみを製造する場合は、酒類製造免許の取得は必要ありません。
参照元:国税庁 酒類製造免許関係
酒類製造免許以外に必要な許可
ビール製造免許を取得しただけでは、ビールを製造することはできません。
都道府県知事が決定した製造施設や、製造設備の基準を満たしているかどうかを保健所に審査してもらったのち、「酒類製造業の営業許可」を受ける必要があります。
酒類製造業の営業許可を受けるには、地域ごとに定められた申請手数料を支払います。
例として、東京都の申請手数料は、新規に営業許可を受ける場合は2万1,600円、更新する場合は1万4,000円です。
また、製造したビールを販売する場合は、販売所がある場所を管轄している税務署から酒類販売業免許を受けなければなりません。
酒類販売業免許も酒類製造免許と同様に、取得に際して登録免許税を支払います。
一部の酒類販売業免許の概要や登録免許税を以下の表にまとめましたので、ご参考になさってください。
【ビールの販売に要する免許】
| 名称 | 概要 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| ビール卸売業免許 | ビールを卸売りできる | 販売所ごとに9万円 |
| 一般酒類 小売業免許 | 販売所においてすべての品目の酒類を小売りできる | 販売所ごとに3万円 |
| 通信販売酒類 小売業免許 | 2つの都道府県を対象に、インターネットやカタログなどから酒類を販売できる | |
| 特殊酒類 小売業免許 | 自社の役員や従業員に継続的に酒類を販売できる |
ほかにも、自分で作成したお酒を海外で卸売りする場合は「輸出入酒類卸売業免許」を取得するなど、販売先や販売方法によって取得する免許が変わります。
参照元:国税庁 酒類製造免許関係
参照元:税務署 酒類卸売業免許申請の手引
関連記事:ビール製造免許とは?取得要件となる製造量についても紹介
酒税法上の「ビール」の定義を押さえる
酒税法では、ビールは麦芽・ホップ・水を基本原料とし、副原料の範囲と使用比率によって発泡酒と明確に区別されます。
- ビールは「麦芽・ホップ・水」が基本原料だから品目判定ができる
- 副原料は政令で範囲が決まるから使用比率でビールと発泡酒が分かれる
- 酒税法の分類で発泡性酒類に位置するから他品目との差異に注意できる
- 定義を誤ると品目外になるから免許の品目整合性でリスクを防げる
それぞれの要点を確認し、ビール製造における品目整合性を確保しましょう。
ビールは「麦芽・ホップ・水」が基本原料だから品目判定ができる
酒税法第3条第12号は、ビールをアルコール分20度未満の酒類として定義しており、その中核となるのが麦芽・ホップ・水という3つの基本原料です。麦芽とホップ、水のみを原料として発酵させたものは、麦芽比率100%のビールとして分類されます。
麦芽とは大麦を発芽させて乾燥させたもので、ビールの風味や色合いを決定づけるものです。ホップはビール特有の苦味と香りを生み出し、水は発酵に不可欠な媒体となります。基本原料の組み合わせが確定していることで、製造者は品目判定の第一段階を明確に把握できます。
関連記事:クラフトビール作りに欠かせない!ビールの5つの原材料
副原料は政令で範囲が決まるから使用比率でビールと発泡酒が分かれる
酒税法施行令第6条では、ビールに使用できる副原料が政令で厳格に定められており、以下が認められています。
- 麦
- 米
- とうもろこし
- こうりゃん
- ばれいしょ
- でん粉
- 糖類
平成29年度の改正により、果実やコリアンダーなどの香味料も追加されました。ビールとして分類されるには、麦芽の重量がホップおよび水以外の原料が50%以上である必要があります。
また、政令で定める副原料の重量の合計が麦芽の重量の5%を超えないことが条件です。この5%という閾値を超えると自動的に発泡酒に区分されるため、製造者は原料の配合比率を事前に精密に設計する必要があります。
酒税法の分類で発泡性酒類に位置するから他品目との差異に注意できる
酒税法第2条では、酒類を発泡性酒類・醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類の4種類に大別しており、ビールは発泡性酒類に分類されます。発泡性酒類には、ビール・発泡酒・そのほかの発泡性酒類が含まれ、それぞれ原料や製法によって細分化されています。
ビールと発泡酒は麦芽比率や副原料の使用範囲によって明確に区別されるため、製造者は品目間の差異を正確に理解しておきましょう。
定義を誤ると品目外になるから免許の品目整合性でリスクを防げる
酒類製造免許は品目ごとに付与されるため、申請時に記載した品目と実際に製造する酒類が一致していなければ、免許の効力がおよびません。ビールの定義を誤って理解し、発泡酒に該当する酒類をビール免許で製造した場合、無免許製造とみなされ、酒税法違反として免許取消しや刑事罰の対象となります。
品目外の製造リスクを防ぐには、申請段階で製造計画を詳細に設計し、原料の配合比率や製造工程を明示することが重要です。税務署の審査では、申請書類に記載された製造計画が酒税法の定義に適合しているかが厳格にチェックされます。
最低製造数量基準の要点(ビールは年60kL以上)
酒税法第7条第2項は品目ごとに最低製造数量基準を定めており、ビールは年間60kL以上の製造見込みが必須となります。
- 最低製造数量は免許要件だから年60kL未達だとビール免許は下りない
- 品目ごとに閾値が異なるから製造計画は品目別に設計する
- 緩和の例外は特区などに限られるから一般要件と混同しない
- 改正経緯を把握できるから数量根拠の説明がしやすくなる
最低製造数量基準の要点を確認し、免許取得に向けた製造計画を適切に策定しましょう。
最低製造数量は免許要件だから年60kL未達だとビール免許は下りない
酒税法第7条第2項は、ビールについて年間60kL以上の製造見込みを要件としています。この基準を満たさない申請は、絶対的拒否要件に該当し、ほかの要件を満たしていても免許が付与されません。
60kLという数量は、大瓶換算で約10万本に相当します。最低製造数量基準は、免許を受けたあと1年間の製造見込み数量として申請書に記載する必要があります。
税務署の審査では、申請者が60kL以上の製造能力がある設備を保有しているか、原料の調達計画が妥当かなどが総合的に判断されるので要注意です。免許取得後も、3年間連続して製造数量が60kLを下回った場合、免許取消しの対象となります。
品目ごとに閾値が異なるから製造計画は品目別に設計する
最低製造数量基準は、品目ごとに異なる閾値が設定されています。ビールは年間60kL以上、発泡酒は年間6kL以上、清酒は年間60kL以上、単式蒸留焼酎は年間10kL以上です。この差異は、各品目の市場規模や製造コスト、酒税の納税額などを考慮して設定されています。
複数の品目を同一製造場で製造する場合、合算して基準を満たせば両方の免許を取得可能です。品目ごとの閾値を把握し、製造計画を品目別に設計することで、免許取得のハードルを適切に管理できます。
緩和の例外は特区などに限られるから一般要件と混同しない
最低製造数量基準には、構造改革特別区域法に基づく特区制度による緩和措置が存在します。特区内で地域の特産物を原料として果実酒を製造する場合、最低製造数量基準が年間6kLから2kLに緩和されます。ただし、ビールに関しては特区制度による緩和は原則として適用されません。
一部の特区では、最低製造数量基準の見直しが検討されることがあります。一般的な要件としては年間60kL以上という基準が維持されています。特区制度は地域活性化を目的とした例外的な措置であり、すべての事業者に適用されるわけではありません。
改正経緯を把握できるから数量根拠の説明がしやすくなる
ビールの最低製造数量基準は、平成6年4月の酒税法改正により、年間2,000kLから60kLへと大幅に引き下げられました。この改正により、中小規模の醸造所がビール製造に参入できるようになり、地ビールブームが起こります。改正の背景には、酒類市場の多様化や地域振興の推進といった政策目的がありました。
60kLへの引き下げにより、小規模事業者が参入可能となり、個性豊かなクラフトビールが全国各地で製造されるようになりました。改正経緯を把握しておくことで、製造計画の数量の根拠を説明する際に、基準の意義を示すことができます。
酒類製造免許を取得するための要件
前述した酒類製造免許には、取得に際して取得要件と拒否要件が設けられています。
それぞれ詳しく紹介していきます。
取得要件
酒類製造免許の取得要件には、年間の最低製造数量が挙げられます。
ビールの最低製造数量は年間60kL以上、発泡酒は年間6kL以上と、製造するお酒の種類によって数量が異なります。
ビールを製造する場合、ビール製造免許を取得してから1年以内に、製造見込み数量が60kL以上を超えなければ、免許を取得できません。
仮に免許を取得できても、3年以上最低製造数量が60kLを下回れば、免許は取り消されることを留意してください。
参照元:国税庁 酒類の製造免許の取消し及び第13条 酒母等の製造免許の取消し
拒否要件
拒否要件とは、設定された項目に該当する場合、免許を受けられない条件を指します。
酒類製造免許の拒否要件は下記の表にまとめた通り、大きく5つに分けられます。
【酒類製造免許における拒否要件】
| 人的要件(一部) | ・酒類製造免許または酒類製造の営業許可を取り消された日から、 3年経過していない場合 ・申請時に未成年者の法定代理人や法人の役員、製造所の支配人が 欠格事由に該当する場合 ・禁固以上の刑の執行終了後、3年が経過していない場合 ・免許の申請前2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けて いる場合 など全10項目 |
|---|---|
| 場所的要件 | 正当な理由なく、取り締まり上不適切と認められる場所に製造場を設置する場合(酒類の製造場または販売場、酒場、料理店などと同一の場所など) |
| 経営基礎要件 | 経営の基礎が薄弱であると認められる場合(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでないなど) |
| 需給調整要件 | 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、免許を与えることが適当でないと認められる場合 |
| 技術・設備要件 | 酒類の製造について、必要な技術的能力を備えていないと認められる場合、または製造場の設置が不十分と認められる場合 |
酒類製造免許の人的要件は、国税庁のホームページで全項目を閲覧できますので、免許の取得申請前に、ご確認ください。
参照元:国税庁 酒類製造免許関係
申請から交付までの流れと登録免許税の扱い
酒類製造免許の取得は、事前相談から申請、免許通知書の交付まで一連のプロセスを経て完了します。
- 事前相談から申請と現地確認まで段取り化できる
- 付与決定後に登録免許税15万円を納付するから資金手当を前倒しにできる
- 納付確認後に製造免許通知書が交付されるから開業日を逆算できる
- 通知は約束ではないから審査余裕を見込んだスケジュールにできる
申請から交付までの流れを確認し、免許取得に向けた段取りを整えましょう。
事前相談から申請と現地確認まで段取り化できる
酒類製造免許の申請は、製造場の所在地を管轄する税務署への事前相談から始めます。事前相談では、事業計画の概要や製造場の設備構想、原料の調達計画などを説明し、免許取得の可能性を確認します。
税務署の酒類指導官から、申請に必要な書類や留意点についてアドバイスを受けることで、申請書類の不備を未然に防ぐことが可能です。申請書類の準備が完了したら、税務署に正式に申請します。
申請後、税務署で審査が行われ、必要に応じて来署依頼や現地確認が実施されます。現地確認では、製造場の設備が申請書類の記載と一致しているか、衛生管理体制が整備されているかなどを確認するのが通常です。
付与決定後に登録免許税15万円を納付するから資金手当を前倒しにできる
免許付与が決定したあと、申請者は登録免許税を納付する必要があります。登録免許税は、免許1件につき15万円と定められており、ビールと発泡酒の両方の免許を取得する場合には、合計30万円が必要です。
税務署から登録免許税の納付案内(納付書など)が示されますので、通知書に従って納付先・方法は案内の指示に従います(税務署窓口、金融機関、電子納付など)。登録免許税の納付は、免許付与の決定後に行われるため、申請段階で支払いは発生しません。
ただし、免許通知書の交付を受けるには登録免許税の納付が必須となるため、資金手当を事前に準備しておくことが重要です。
納付確認後に製造免許通知書が交付されるから開業日を逆算できる
登録免許税の納付が確認されると酒類製造免許通知書が交付されます。免許通知書の交付をもって、正式に酒類製造免許が付与され、製造場での酒類製造が法的に認められます。
製造免許通知書を受領した日から、酒類の製造を開始することができるため、開業日を逆算してスケジュールを組むことが重要です。免許申請から交付までの期間は、標準処理期間は申請書の受付から4か月が目安です。補正が必要な期間は標準処理期間から除外されます。
通知は約束ではないから審査余裕を見込んだスケジュールにできる
酒類製造免許の標準処理期間は、原則として申請書の受付から4か月とされていますが、これはあくまで目安であり、確約された期間ではありません。審査の過程で申請書類の補正や追加資料の提出を求められた場合、補正対応に要した期間は標準処理期間から除外されます。
審査期間の延長を避けるには、申請書類を精緻に作成し、不備や矛盾がないよう事前に確認することが重要です。免許取得を前提に事業計画を進める場合、標準処理期間に加えて、補正対応や審査状況の変動を見込むことが推奨されます。
公式の標準処理期間は4か月ですが、補正・設計変更・繁忙期などで延びることがあるため、実務上は+ 2〜8か月程度の余裕を見込む計画が安全です(公式期間ではありません)。その期間を前提に資金計画や設備導入のスケジュールを組むことが安全です。
食品衛生法とHACCPの整理(酒造への適用)
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品など事業者(酒造を含む)にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。
- HACCPは義務化だから酒造も衛生管理計画の整備が必要になる
- 小規模は考え方を取り入れた衛生管理で対応できる
- 国税庁も周知しているから酒造向けの要点で確認できる
- 営業許可制度は別枠だから施設基準は参照しつつ衛生環境を整える
HACCPの要点を確認し、酒類製造業における衛生管理体制を整備しましょう。
HACCPは義務化だから酒造も衛生管理計画の整備が必要になる
平成30年6月に公布された「食品衛生法などの一部を改正する法律」により、令和3年6月1日から、酒類製造業を含むすべての食品など事業者に対して、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されました。
HACCPとは、危害要因分析と重要管理点を意味する国際的な衛生管理手法です。酒類製造業者は、製造工程における危害要因を分析し、重要管理点を設定した衛生管理計画で実施する義務があります。
小規模は考え方を取り入れた衛生管理で対応できる
食品の取扱いに従事する者の数が50名未満の小規模事業者は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施すれば足り、HACCP7原則すべてを導入する必要はありません。
酒類製造業界では、業界団体が「酒類製造業におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模事業者向け)」を作成しています。
手引書には、衛生管理計画のひな形や記録様式が含まれており、小規模事業者はこれを参考に自らの製造場に適した衛生管理計画を作成しましょう。
国税庁も周知しているから酒造向けの要点で確認できる
国税庁は、酒類製造業者に対してHACCPの義務化について周知活動を行っており「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について」というリーフレットを作成しています。
国税局の鑑定官室では、酒類製造業者からのHACCPに関する技術相談を随時受け付けています。国税庁のリソースを活用し、酒類製造業に特化した衛生管理体制を整備することが重要です。
営業許可制度は別枠だから施設基準は参照しつつ衛生環境を整える
酒類製造業は、酒税法に基づく製造免許とは別に、食品衛生法に基づく営業許可を保健所から取得する必要があります。営業許可は、製造場の施設が都道府県の条例で定める施設基準に適合していることが条件となります。
施設基準の確認は、製造場の設計段階で行うことが重要です。建築工事の着工前に、保健所に設計図面を持参して事前相談を行い、施設基準に適合しているかを確認します。
酒類製造免許を取得するための費用と申請方法
酒類製造免許の取得では、免許1件につき登録免許税15万円を納入します。
さらに、酒類製造免許の取得申請に代行サービスの利用を検討されている方は、平均10万~20万円の費用がかかることを考慮しましょう。
酒類製造免許を取得するためには、ご自身の製造所を管轄している税務署へ、製造したい種類の品目別・製造所ごとに申請書を提出します。
申請書の提出手段は、オンラインまたは税務署への直接の提出か、郵送するかを選ぶことができます。
オンラインで申請書を提出する際は、e-Taxホームページ内の「e-Taxソフトについて」より、詳細をご確認ください。
なお、申請から審査終了までの所要時間は、2~3週間程度です。
申請書を提出してから営業を開始するまでの流れは、以下を参考になさってください。
【酒類製造業の営業許可を取るまでの手続き】
- 保健所と事前相談
- 醸造所着工
- 申請書類の提出
- 醸造所検査
- 認可証の交付
- 営業開始
保健所の許可なく酒類を製造した場合、営業停止・行政処分や、処罰の対象となる可能性がありますので、絶対にやめましょう。
参照元:e-Tax(国税電子申告・納税システム) e-Taxソフトについて
参照元:国税庁 酒類の製造免許の申請
ビール製造免許の登録免許税は免許1件につき15万円
今回は、ビール製造免許の概要や、免許の取得にかかる費用などをお伝えしました。
ビール製造免許の取得には、登録免許税として15万円の費用がかかります。
ビール製造免許のほかにも、酒類製造業の営業許可を受けるための申請手数料として、東京都では新規2万1,600円、更新1万4,000円を支払います。
製造したビールを販売する際は、販売方法や販売先によって免許1件につき3万~9万円の登録免許税がかかることも、ご承知おきください。
マイクロブルワリー、クラフトビール開業支援のスペントグレインは、ビール醸造所の立ち上げに関することなら何でもお手伝いします。
ビール職人が考え抜いた、使いやすい醸造設備のご提案から発注まで承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
コンビタンクブリューハウスの製品説明はこちら
発酵タンクの製品説明はこちら
この記事の監修者
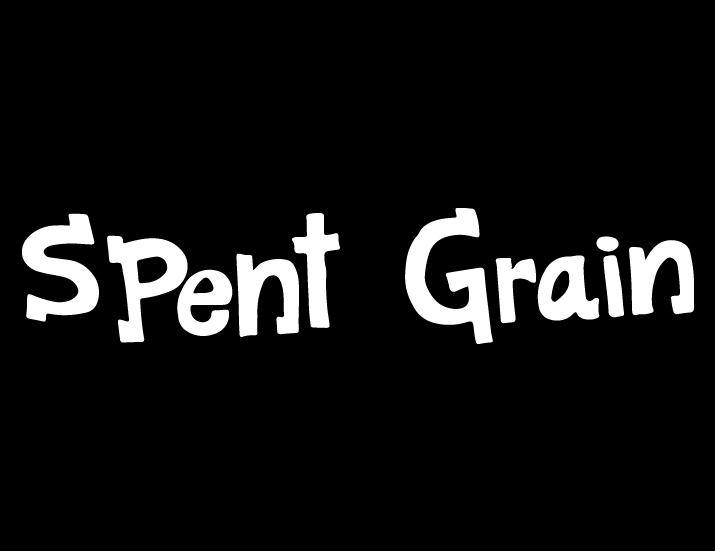
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。