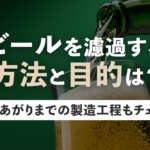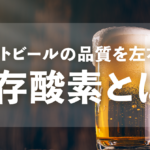ビールケグの種類と容量まとめ|飲食店やブルワリーが導入前に知るべきこと
- 技術・ノウハウ
- 2025.09.08
- 2025.12.19

クラフトビールや業務用ビールを扱う現場では「ビールケグ」と呼ばれる容器が欠かせません。
ビールケグは瓶や缶よりも効率的にビールを保存でき、鮮度を長く保てるため、広く利用されています。
飲食店やブルワリーにとって、ビールケグは単なる容器ではなく、品質を守るための重要な設備です。
本記事では、ビールケグの基本的な特徴や種類から容量の違い、使用後の取り扱い方法までを体系的に解説します。
ビール提供に関わる方の理解を深めることを目指します。
ビール醸造で使用するケグとは?
ケグとは、ビールを密閉して保存し、ガス圧を利用して注ぐための円筒形容器です。
内部が外気に触れないため酸化を防ぎ、鮮度を長く保てます。
ステンレス製が主流で、何度も洗浄・再利用できる点も大きな特徴です。
飲食店やイベント会場ではビールサーバーに接続して使用され、均一で安定した品質を維持したまま多くの人に提供できる仕組みになっています。
瓶や缶よりも効率的に管理でき、クラフトビールや大手メーカー双方に欠かせない存在です。
ケグとカスクの違い
ビールの提供に使われる容器には「ケグ」と「カスク」があり、それぞれ仕組みが異なります。
ケグは外部から二酸化炭素を注入し、ガス圧でビールを押し出すため、長期間にわたって安定した品質を保てます。
一方、カスクは樽内で自然に二次発酵を行い、その際に発生する炭酸ガスでビールを注ぐ仕組みです。
人工的なガスを加えないため、風味が繊細に変化しやすく、リアルエールとして提供されることが多いのが特徴です。
効率性を重視する場合はケグ、伝統的な風味を楽しみたい場合はカスクと、目的やスタイルに応じて選ばれています。
関連記事:ケグとカスクの違いを項目別に解説
ビールケグの種類
ビールケグは素材によって特徴が異なり、用途や規模に合わせて選ぶことが大切です。
ステンレス製は耐久性に優れ、プラスチック製は軽量で扱いやすいという強みがあります。
- ステンレス製
- プラスチック製
これらの違いを理解すると、導入時の選択を誤らずに済みます。
以下で、それぞれを詳しく見ていきましょう。
ステンレス製
ステンレス製ビールケグは耐久性と再利用性に優れたもっとも一般的なタイプです。
衝撃に強く、繰り返し洗浄して使用できるため、長期的な運用に適しています。
外気を遮断する性能が高いためビールの酸化を防ぎ、提供品質を安定させやすいのも利点です。
一方で重量があり、運搬や設置に体力を要する点には注意が必要です。
居酒屋やホテルなど継続的に大量のビールを提供する現場では信頼できる選択肢となります。
さらにステンレスは熱伝導率が低いため、温度変化が少なく保管中のビールが傷みにくいのも特徴です。
衛生面でも強く、洗浄時に熱水や薬剤を使っても劣化が少ないため、常に清潔な状態を維持できます。
国内外の大手メーカーが標準として採用しているのも、こうした強みがあるからです。
長年の実績と信頼性を考えると、初めてビールケグを導入する場合でも安心して選べるのがステンレス製となります。
ステンレス製は世界的にも標準的に使われており、国際的なビール流通でも信頼性が高い容器です。
再利用サイクルが確立しているため、環境負荷の低減にもつながります。
また高圧に耐える構造を備えているため、炭酸が強めのビールにも対応可能です。
とくに輸送距離が長い場合や、温度変化の大きい倉庫環境でも品質を保ちやすい点は大きな強みです。
結果的にロスを防ぎ、安定的に顧客へ提供できる体制を整えられます。
プラスチック製
プラスチック製ビールケグは軽量で扱いやすく、比較的新しいタイプです。
ステンレス製に比べてコストを抑えられる場合もあり、イベントや短期間の利用に適しています。
スタッフの負担を軽減できる一方、耐久性や再利用性は金属製に劣るため、長期的な使用には向きません。
マイクロブルワリーや限定イベントなど、短期間で効率的にビールを提供したい場面で活躍します。
効率とコストのバランスを取るには、提供の規模や用途に応じて適切に選ぶことが重要です。
またプラスチック製は透明性のある素材を使った製品もあり、残量が外から分かりやすいというメリットがあります。
重量が半分程度になるため、女性スタッフや少人数の店舗でも扱いやすいのも強みです。
一方で紫外線や熱に弱く、長期間の保存には不向きです。
そのため輸送用や短期間のイベントなどでの利用に限定されることが多くなっています。
導入コストを抑えたい、あるいは限定イベントで大量に必要になる、といったケースでは大きな利点です。
加えて、プラスチック製は導入コストの低さや軽量性に加え、輸送コスト削減にも関係します。
航空便や宅配便を使った小ロット出荷の際にも利便性が高く、小規模ブルワリーが販路を広げる際に選ばれるケースも増えています。
また一部の製品はリサイクルを前提に作られており、使い捨て後も資源として再利用が可能です。
使いやすさと環境面での配慮を兼ね備えていることから、今後さらに導入事例が増えると予想されています。
ケグの容量
ビールケグは7〜20Lまで幅広い容量が存在し、国内大手メーカーでも用途に応じて使い分けられています。
容量が大きいほど一度に多くのビールを提供できますが、重量も増すため扱いには注意が必要です。
小規模店舗や家庭利用には小型が便利で、大規模飲食店や宴会場では中〜大型が適しています。
以下は代表的な容量とサイズ・重量の目安です。
| 容量 | 高さ | 直径 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 7L | 約35cm | 約23cm | 約3.5kg |
| 10L | 約40cm | 約23cm | 約4.5kg |
| 15L | 約47cm | 約25cm | 約6.0kg |
| 20L | 約50cm | 約26cm | 約7.5kg |
容量ごとの特徴を理解し、規模や回転率に合ったサイズを選ぶことで、効率的で鮮度の高いビール提供が可能になります。
また、ビールケグの容量はスタッフの作業負担や保管スペースにも影響します。
大容量のビールケグは提供効率が上がる一方、保管場所の確保が必要です。
小容量のビールケグは運搬しやすい反面、交換の頻度が高くなります。
どの容量を選ぶかは、提供環境や人員体制を考慮したうえで、総合的に判断することが大切です。
ケグの容量別のビール杯数の比較
容量の違いは単なるサイズだけでなく、提供できる杯数にも直結します。
一般的に中ジョッキ1杯を350mlとして換算すると、以下に相当します。
| 容量 | 杯数(約350ml換算) |
|---|---|
| 7L | 約20杯 |
| 10L | 約28杯 |
| 15L | 約43杯 |
| 19L | 約54杯 |
| 20L | 約57杯 |
小規模な店舗で大容量のビールケグを使うと、回転率が低いため鮮度が落ちやすいです。
一方、繁盛店で小型のビールケグを使うと、交換頻度が増えてスタッフの負担が大きくなります。
杯数を基準にビールケグを選ぶことは、業務効率と品質維持の両立に役立ちます。
また、杯数の目安を把握しておくことで、仕入れ計画やコスト管理がしやすいでしょう。
宴会シーズンやイベントでは、大容量のビールケグを選ぶことで交換回数を減らし、繁忙期の混乱を防げます。
反対に、日常営業では小型のビールケグを組み合わせて使うことで、常に新鮮なビールを提供できるというメリットがあります。
空になったビールケグはどうする?
ビールケグは使い切ったあとに必ず回収や洗浄を行う必要があります。
多くの場合、酒販店が回収してメーカーや工場で内部を徹底的に洗浄・殺菌し、再利用するのが一般的です。
ステンレス製であれば耐久性が高く、このサイクルを長期間繰り返せます。
一方、小規模な醸造所では自前の装置で洗浄する場合もあり、コストを抑えて再利用できるのが利点です。
ただし洗浄不足は品質劣化につながるため、衛生管理を徹底することが求められます。
適切な管理を行うことで、次回も鮮度の高いビールを提供できるのです。
さらに回収されたビールケグは、外装の状態もチェックされます。
凹みや劣化があれば修繕や交換が行われ、安全に再利用できる状態に保たれます。
こうした仕組みは環境負荷を抑えるうえでも有効です。
飲食店にとっても回収システムを活用することで在庫管理がしやすくなり、限られたスペースを有効に活用できる点も大きなメリットです。
まとめ
ケグは、鮮度を保ちながら効率的にビールを提供できる容器であり、飲食業界やブルワリーにとって欠かせない存在です。
素材や容量ごとの特徴を理解し、店舗の規模や目的に合ったビールケグを選ぶことが、無駄のない運営と高い顧客満足度につながります。
また、使用後は必ず回収や洗浄を行うことで、品質を維持しながら継続的な運用が可能です。
ビールケグの導入や設備選びで迷った場合は、現役ブルワーが支援する「スペントグレイン」までご相談ください。
経験をもとに最適な提案を行い、理想的なビール提供の実現をサポートします。
さらに、ビールケグを正しく使いこなすことは、店舗経営の信頼性向上にもつながります。
鮮度の高いビールを常に提供できる店舗は、顧客のリピート率が自然と高まるでしょう。
効率的なオペレーションは、人件費や廃棄ロスの削減にも役立ちます。
設備投資と管理をバランスよく行うことで、ビール提供は単なるサービスから店舗の「強み」となります。
ツーベッセルの製品説明はこちら
ブリューハウスの製品説明はこちら
この記事の監修者
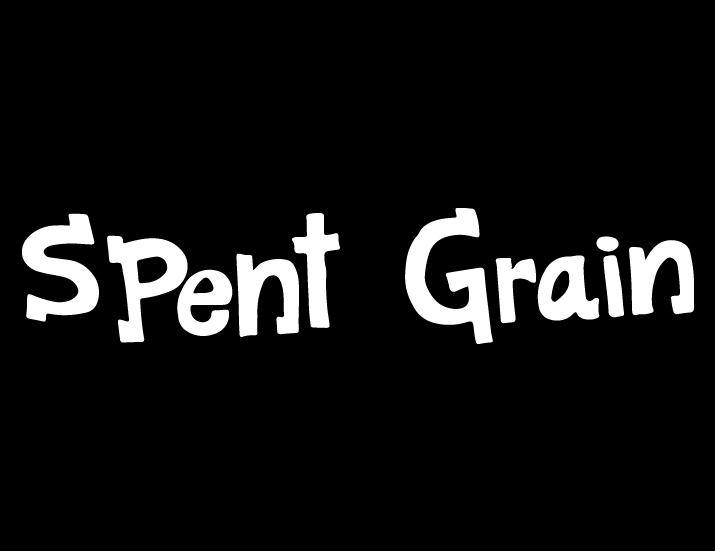
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。