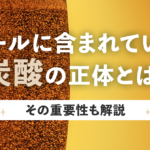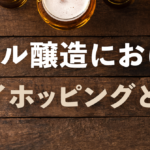ビールの麦芽比率とは?発泡酒との定義の違いと酒税について
- 原材料
- 2025.02.21
- 2025.12.19

ブルワリーの新規立ち上げや事業拡大を検討している方に向けて、ビールの麦芽比率について解説いたします。
麦芽比率はビールとなるか、発泡酒となるかの違いを決める大きな要素です。
しかし麦芽比率だけで決められるものでもなく、その他に原材料以外の原料の内容や使用量も関係してきます。
条件は複雑ですので、今回の記事では、ビールと発泡酒の違いを麦芽比率の観点から解説します。
参考にしていただければ、麦芽の比率による酒税の違いまで把握していただけるはずです。
【目次】
ビールを定義する麦芽使用比率とは
まずビールを定義する『麦芽使用比率』とは、ビールの原料中に占める麦芽の割合を指します。
「ビール」と表記するには、水・ホップ・酵母以外の麦芽を使う割合が5割以上でなければなりません。
一例をあげてみます。
| ビール表記 | 原材料 | 麦芽を用いる割合 |
| ○ | 麦芽100% | 100% |
| ○ | 麦芽80%、その他20% | 80% |
| × | 麦芽49%、その他51% | 49% |
麦芽を使う割合が5割以上であればビールと表記できますが、5割未満ではビールとはみなされません。
ビールと表記できるかどうかは、商品の種類が変わるだけでなく、酒税にも影響を及ぼします。
そのため製造段階で、どの原料をどのくらい用いるかを決めておく必要があります。
このように、ビールの定義には麦芽比率が深く関わっています。
ビールと発泡酒の違いを定義する項目
ビールと発泡酒の違いを定義する要素には、「麦芽を使うわりあい」と「原材料以外の原料の内容」「原材料以外の原料の使用比率」の3つがあります。
最初に麦芽を使う割合と風味を調整するための原料について簡単にまとめてみました。
| 表記 | 麦芽を用いる割合 | 原材料以外の原料の内容 | 原材料以外の原料の使用比率 |
| ビール | 5割以上 | 法律で規定されているもの | 麦芽の重量の5%以下 |
| 発泡酒 | 5割以上 | 法律で規定されているもの | 規定量を超える |
| 発泡酒 | 5割以上 | 法律で規定外のものを含む | 麦芽の重量の5%以下 |
| 発泡酒 | 5割以上 | 法律で規定外のものを含む | 規定量を超える |
| 発泡酒 | 5割未満 | 法律で規定外のものを含む | 規定量を超えない |
ビールとして認められるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
麦芽を使う割合が5割以上であっても、風味を調整するための原料の内容や使用比率によってはビールとは表記できません。
次に、ビールと発泡酒の違いを明確にするため、麦芽の割合と原材料以外の原料について詳しく解説します。
麦芽使用比率
麦芽比率はビールを定義づけるものでもあり、発泡酒との違いを明確にする要素でもあります。
原材料のうち、麦芽が5割以上使用されていなければビールと表記できないと、最初に解説しました。
つまり麦芽が5割未満しか使用されていない場合、ビールではなく発泡酒となります。
以前は、麦芽を使用する割合が67%以上のものだけがビールと表記できる決まりでした。
しかし平成29年度の税制改正によりビールの定義も変わり、麦芽を使う割合5割以上であればビールと表記できるように。
その結果、以前は発泡酒とされていたものも、ビールと表記できるようになりました。
以上のように令和7年度現在では、麦芽を使う割合5割以上のものがビール、5割未満であれば発泡酒と位置づけられています。
副原料の種類
ビールと発泡酒の定義では、原材料以外の原料の種類についても定められています。
原材料以外の原料とは、麦芽・水・ホップ・酵母以外の材料を指します。
香り付けや苦みの添加、着色のために使われるものが副原料と呼ばれています。
ビールと表記するために許される原料は、法律によって決められています。
風味を調整するための原料として使用できるものは税制改正によりさらに拡大されました。
今まで「ビール」に副原料として使用できるのは米,麦,トウモロコシに限られていたが,改正後は果実や香辛料等,具体的には,サツマイモ・かぼちゃなどの野菜のほか,蕎麦,蜂蜜,食塩,味噌,コショウ,シナモン,バジル,海産物である牡蠣や昆布,鰹節,さらにはコーヒー等の使用が認められるようになった.
出典:JSTAGE:(PDF)ファルマシア・54巻・10号・1008頁
しかし法律で定められているもの以外の風味を調整するための原料を使った場合、麦芽を使う割合に関係なくビールとの表記はできません。
ただし、法律で定められていない原料を使用しても法律違反にはなりません。
あくまでもお酒としての種類が変わるだけです。
どのような原料を使用しても問題ありませんが、その場合は発泡酒に分類されます。ビールを製造する際は、風味を調整する原料の選定が重要になります。
副原料の使用量
原材料以外の原料の種類だけでなく、使用量もビールと発泡酒との定義の違いとなります。
ビールと表記するには、規定量を超えてはなりません。
たとえ麦芽を使う割合が5割以上であってもです。
法律で定められた原材料以外の原料を使ったとしても、規定量以上使用している場合は発泡酒となります。
ビールに許される原材料以外の原料の規定量は「使用している麦芽の重量の5%以内」です。
そのため麦芽を使う割合により使用できる量は変わります。
5%を超えて用いるなら発泡酒となることを知っておいてください。
ビールと発泡酒に味の違いはある?
麦芽を使う割合を含め、ビールと発泡酒の定義についてご紹介してきました。
しかしビールと発泡酒に味の違いはあるのでしょうか?
発泡酒には、ビールとは異なる魅力があることも事実です。
味わいの面から、両者にどのような違いがあるのか見ていきましょう。
ビールは原料の味を楽しめる
まずビールの魅力といえば、原料の味を存分に楽しめることです。
麦芽を使う割合が高いことから、麦芽のもつ旨味やコクを堪能できます。
またホップの苦み、香りも強く、発泡酒に比べて濃厚な味わいだと感じられるでしょう。
そのためビールが好きな方であれば、発泡酒では味わいやコクが物足りないと感じることもあるかもしれません。
まったりとした味わいを期待する方にとって、発泡酒は爽やかすぎると思われるはずです。
本来のビールの味わいを堪能したい場合は、発泡酒ではなくビールを選ぶことをおすすめします。
関連記事:クラフトビールと生ビールの違いは?押さえておきたい種類や楽しみ方
発泡酒は味のバリエーションが豊富である
対して発泡酒の魅力は、味のバリエーションが豊富であることです。
先に解説したように、発泡酒には原材料以外の原料が多く使用されている傾向があります。
そのためフレーバーを楽しめ、ビールにはない魅力を感じられるはずです。
商品ごとにフレーバーが異なるので、好みの商品を探す楽しみもあります。
また発泡酒のほうが味わいが軽いことも特徴のひとつ。
ビールは原料特有の濃厚な味わいを感じられますが、発泡酒は軽やかでスカッとしたい方には発泡酒のほうが向いているかもしれません。
発泡酒は、お酒が苦手な方でも飲みやすく、軽やかな味わいと豊富なバリエーションが最大の魅力と言えるでしょう。
麦芽使用比率と酒税の関係
麦芽の使用割合は酒税にも影響を与えます。
令和5年10月に、ビールおよび発泡酒の酒税は次のようになりました。
| 麦芽を使うわりあい5割以上 | 181,000円/kl |
| 麦芽を使うわりあい25~50%未満 | 155,000円/kl |
| 麦芽を使うわりあい25%未満 | 134,250円/kl |
| 発泡酒のうち新ジャンル | 134,250円/kl |
| ホップを原料としない酒類 | 80,000円/kl |
| 麦芽を使うわりあい5割以上 | 181,000円/kl |
参照:国税庁:(PDF)発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き
麦芽の使用割合が高いビールは、酒税も高く設定されています。
しかし令和8年10月以降からは、麦芽比率に関係なくビールと発泡酒、新ジャンルは「155,500円/kl」に統一される予定です。
またホップを原料としない酒類は100,000円/klとなります。
参照:国税庁:(PDF)発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き
そのため、麦芽比率が高いビールは酒税が低く抑えられますが、麦芽の使用割合が25%未満の発泡酒は税率が高くなります。
「新ジャンル」とは
「新ジャンル」とは発泡酒のうち、ホップが原料の一部として用いられているお酒のことです。
「第3のビール」と呼ばれたこともありました。
麦由来のスピリッツと麦芽以外の原料を使用したお酒で、味はビールに近いものになっています。
麦芽以外に使用されるのは豆類で、大豆やえんどうがメインです。
そして発泡酒にスピリッツをプラスしたもの考えて良いでしょう。
これまでも酒税は最も抑えられていましたが、令和8年10月からはこれまでよりも酒税が上がります。
新ジャンルの製法で製造している場合は、酒税改正により価格が上昇する可能性があります。
ビール、発泡酒、新ジャンルのどれを製造するかは、酒税改正を考慮して慎重に判断する必要があります。
麦芽比率はビールの味わいや酒税にも影響する
いかがでしたでしょうか?
この記事をお読みいただき、ビールの麦芽比率についてご理解いただけたのではないでしょうか。
麦芽の使用割合は、ビールと発泡酒の定義や酒税にも大きな影響を及ぼします。
どのくらいの比率で製造するか、あらかじめ決めておかなければなりません。
そこで頼っていただきたいのがスペントグレインのブルワリー支援サービスです。
醸造所のコンサルティングも行っておりますので、麦芽を使う割合を考えたうえで、種類豊富なおいしいビールを製造できるようサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者
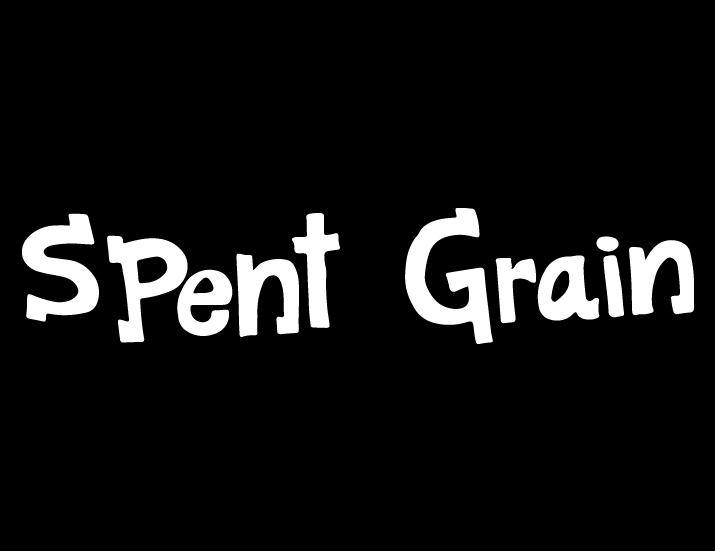
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。