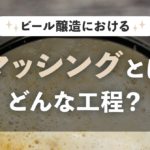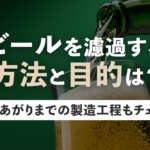クラフトビール造りではスパージングが肝心!その概要を解説
- 技術・ノウハウ
- 2025.02.21
- 2025.08.01
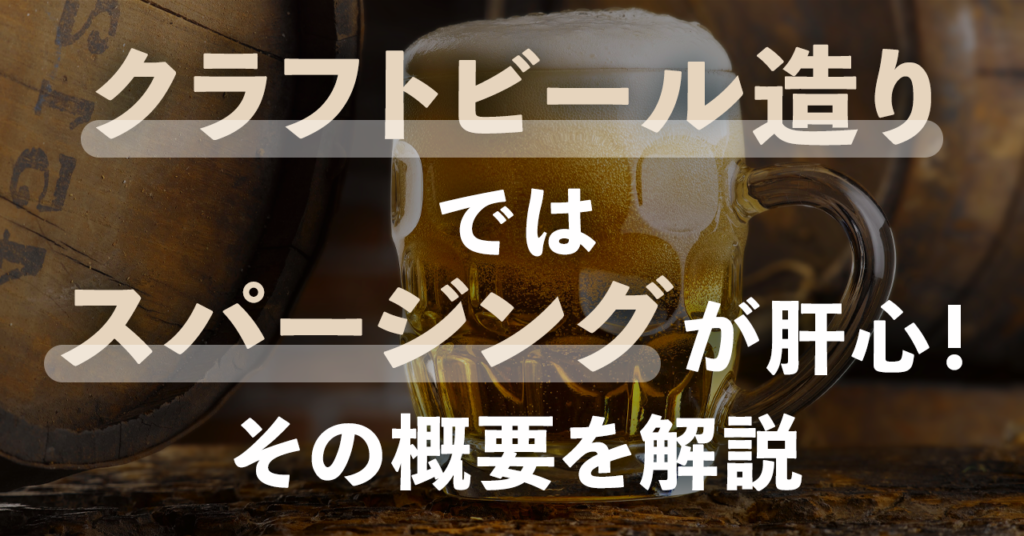
クラフトビール造りにおいて、スパージングは麦汁抽出の効率を左右する重要な工程です。
新規事業として醸造所を立ち上げる、または増設を検討する経営者にとって、具体的な流れや方法を正しく理解することが成功の鍵となります。
そこで本記事では、スパージングの概要や実施方法を詳しく解説します。
スパージングを省略する場合の選択肢や、その前後の工程についても説明します。
効率的な醸造を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
スパージングの概要
スパージングとは、クラフトビール醸造における麦汁抽出のプロセスです。
糖化を終えた麦芽液(マッシング後の液体)から効率的に糖分を回収しながら、モルトと麦汁を分離します。
マッシングの段階で得られる麦汁は、モルトと一体化した状態でお粥のような質感をもっています。
このままではモルトの苦味や不要な成分が抽出される恐れがあるため、スパージングを行うことでそのリスクを回避します。
スパージングの一環として、麦芽層に一定量の温水を加え、モルトに残った糖分を洗い流し、可能な限り有効利用します。
温水をかけることで糖分の抽出効率を高め、モルト粕に残る糖分を最小限に抑えることができます。
このプロセスにより麦汁の収量を増やし、無駄を削減できるのです。
スパージングの流れ
スパージングは、クラフトビール造りにおける麦汁抽出効率を最大化するための重要な工程です。
このプロセスでは、麦芽から糖分を無駄なく取り出すために、いくつかのステップを踏みます。
それぞれの工程を適切に実施することで、ビールの品質向上と効率的な醸造が実現するでしょう。
ロータリング
ロータリングは、麦芽層(グレインベッド)を形成する作業です。
スパージングの準備段階であり、麦芽層を整えることで糖分の抽出効率を高める役割を果たします。
専用のタンク「ロイタータン」を使用し、底部にあるロイター板を通じて麦汁と麦芽を分離します。
最初にロイター板から流れ出る麦汁には、小さなモルト粒が混ざっています。
そのため、この麦汁をタンク上部から再び戻す工程を繰り返し行うことで、粒子が均等に分布し、ろ過効果を発揮するきれいな麦芽層を形成します。
ろ過された麦芽層は、スパージング時に糖分を効率よく回収するためのフィルターの役割として機能。
注意点として、麦芽層に穴やヒビができると糖分回収効率が低下し、濁った麦汁が抽出される原因になります。
そのため、麦芽層の厚さを均等に保ち、穴を防ぐことが重要です。
麦汁比重の計測
ロータリングを終えた段階で、麦汁の比重(First Wort Gravity)を計測します。
比重はビール造りの中間チェックポイントであり、糖化やロータリングが正確に行われたか確認するための重要な指標です。
比重が目標値より低い場合は、次の工程で修正を加える必要があります。
例えば、糖分を追加投入する、煮沸時間を調整するなどの対応が挙げられます。
このタイミングで適切に修正すれば、最終的なビールの品質や方向性を調整できます。
麦汁比重が低い場合の原因
麦汁比重が想定よりも低い場合、次のような原因が考えられます。
- レシピ作成時の計算ミス
- モルト量の誤投入
- マッシング時の糖化の失敗
- ロータリングの精度不足
計算ミスや誤投入などの問題は修正が難しいため、各工程で十分な注意が必要です。
スパージング
スパージングは、形成された麦芽層に温水をかけ、モルトに残った糖分を洗い流して麦汁を抽出する工程です。
この工程では、糖分の回収効率を高めながら麦汁の濃さを調整します。
温水の温度は非常に重要で、適温は74~76℃です。
温度が高すぎるとモルトの殻からタンニンが溶け出し渋みが生じ、低すぎると糖分が十分に回収されません。
温度管理を徹底することで、糖分を効率よく回収しつつ、品質の高い麦汁が得られます。
スパージングを止めるタイミングは、麦汁の比重や品質を目安に判断します。
スパージングを続けることで麦汁の比重が徐々に下がっていきますが、目標とする濃度に達した時点でスパージングを終了するのが一般的です。
さらに、スパージングを続けると糖分がほとんど抽出されなくなり、水っぽい麦汁になることがあるため、適切なタイミングで作業を終了する必要があります。
スパージングの方法
スパージングにはさまざまな手法がありますが、ここでは代表的な「バッチ・スパージング」と「コンティニュアス・スパージング」について解説します。
それぞれの方法には特徴があり、設備や目的に応じて選択することが重要です。
正しい手法を採用することで、糖分の回収効率や麦汁の品質を向上させることができます。
バッチ・スパージング
バッチ・スパージングは、マッシュタンクから麦汁を段階的に抽出し、その都度必要な量の温水を一括で追加する手法です。
まず、麦芽層が麦汁から露出する直前にスパージングウォーターを上から注ぎ、抽出を続けます。
麦芽が均等に温水に浸されることで、糖分を効率的に洗い出す工程です。
バッチ・スパージングでは、温水の量を自由に調整できるため、小規模な設備でも対応しやすいのが特徴です。
また、麦芽層が常に適切に浸された状態を維持することが重要です。スパージングウォーターが不足する場合は、一時的に抽出を停止して対応することができます。
シンプルな方法でありながら、設備への負担が少なく運用しやすいのがメリットでしょう。
コンティニュアス・スパージング
コンティニュアス・スパージングは、麦汁を抽出しながら同じ速度でスパージングウォーターを連続的に供給する手法です。
この方法では、麦汁が煮沸釜へ流れ込む速度と一致するペースで温水を注ぎ続けるため、スムーズに抽出することができます。
糖分の回収効率が非常に高いことがコンティニュアス・スパージングの大きなメリットですが、その一方で、スパージングウォーターを一定速度で供給するための専用設備が必要です。
スパージングの時間は麦芽の量や使用する温水の量によって異なりますが、一般的には30分から120分程度で行います。
スパージングしない場合もある?
高比重の麦汁を得たい場合や、特定のビールスタイルを目指す場合、スパージングしない選択肢もあります。
「1番麦汁」のみを使用するため、高アルコールビールや濃厚な味わいのビールを醸造する場合に適しています。
また、タンニンの抽出が抑えられるため、滑らかでバランスの良い仕上がりになるのも特徴。
さらに、工程が簡略化されることで作業効率が向上するのもメリットです。
ただし、糖分回収率は低下するため、用途や目標に応じて検討する必要があります。
スパージング前後の工程
スパージングはビール醸造において糖分を効率よく回収する重要な工程ですが、その前後のプロセスもビールの品質を左右するため、合わせて覚えておきましょう。
ここではスパージング前の『マッシング』とスパージング後の『ワールプール』について解説します。
マッシング
マッシングはビール醸造の最初の工程で、麦芽を温水に浸してデンプンを糖分に分解するプロセスです。
この工程で得られる糖分はビールの発酵に必要で、味わいやアルコール度数を決定する重要な役割を果たします。
マッシングでは適切な温度管理が求められ、一般的には60~70℃の範囲で行われます。
温度によって生成される糖分の種類が異なり、低温では発酵性の高い糖分が多く生成され、スッキリとしたビールに仕上がります。
高温では非発酵性糖分が増え、濃厚でボディ感のあるビールに仕上がります。
さらに、水質もマッシングの品質に大きく影響します。
適切なpH(5.2~5.4)とミネラルバランスが酵素の働きを最適化し、糖分の分解を効率よく進めることができます。
マッシングが成功すれば、スパージングで糖分を効率的に回収しやすくなり、全体の工程をスムーズに進めることができます。
ワールプール
ワールプールはスパージング後に行われる工程で、煮沸した麦汁から不要な固形物を除去し、ビールの透明度と品質を向上させることを目的としています。
この工程では、煮沸釜または専用のワールプールタンクに麦汁を高速で循環させ、遠心力によって凝固物(トルーブ)をタンクの中心に集めます。
この過程でタンパク質やホップの残渣、酸化物などが分離され、滑らかでクリアな麦汁を得ることができます。
ワールプールは、麦汁の冷却や発酵準備を整えるための重要なステップでもあります。
正しく行うことで、ビールの風味や香りに影響を与える不要な雑味を除去し、発酵時の酵母が最大限に働く環境を整えることが可能です。
スパージングでクラフトビールの品質を左右する
いかがでしたでしょうか?スパージングについての概要や実施方法、省略する場合の選択肢についてもお分かりいただけたかと思います。
スパージングはクラフトビール造りの品質と効率に直結する重要な工程で、スムーズな醸造を実現するために、適切な設備と手法を選択することが重要です。
また、マイクロブルワリーやクラフトビール開業をお考えの方は、醸造支援を行う「スペントグレイン」の利用がおすすめです。
現役醸造家が運営する当社では、使いやすい醸造設備を提供するとともに、個別のニーズに応じたカスタマイズにも対応しています。
クラフトビール事業の設備を検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者
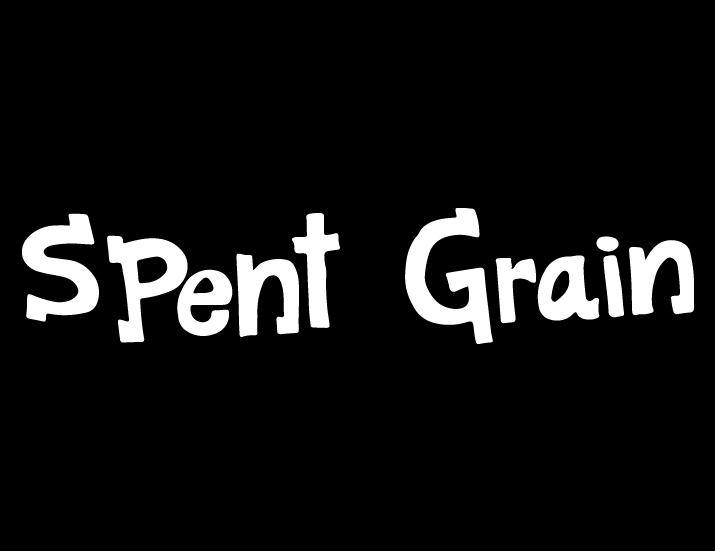
株式会社スペントグレイン
マーケティング担当者
兼 醸造アドバイザー/経営コンサルタント
<略歴>
大手経営コンサルティング会社へ就職し、地域経済の活性化に貢献するプロジェクトに多く携わり、食品やアルコールを通じた地域振興・施設開発を専門にコンサルティングを行う。経営アドバイザー・醸造アドバイザーとして地域密着型のクラフトビール事業の立ち上げから設備導入、経営戦略までを一貫して支援し、地元の特産品を活かしたビールづくりにも取り組んでいる。
<監修者から>
ビールの品質は、技術は当然のことながら、経営の安定からも生まれます。持続可能で収益性の高い事業運営を支援しながら、ビールの味わいを最大限に引き出すことが私の使命です。 良い設備がなければ、良いビールは生まれません。しかし、経営が安定してこそ、長期的に持続可能なビール文化を築けるのです。